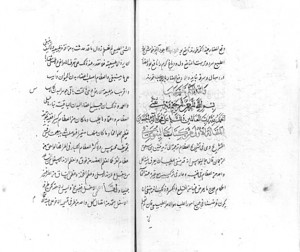アッバース帝国とギリシア医学の翻訳
7世紀から8世紀にかけて、イスラームがアラビア半島からその周囲の広大な領域に広がり、サーサーン朝ペルシアを滅ぼし、ビザンティン帝国の領土の中に食い込み、エジプトなどに広がった。その過程で、ギリシア医学のテキストが集積している地も征服されていった。エジプトのアレクサンドリアは、正統カリフ時代のカリフであるウマール(在位717-720)によって征服され、その文化的な資産はアンティオキアに移されることとなった。
しかし、古代医学の遺産、ことにギリシア医学のテキストのアラビア語への翻訳が本格化したのは、アッバース朝の時代のカリフやエリートたちの支持によるものであった。アラブ民族による支配と捉えられるウマイヤ朝を倒して、アッバース朝はアラブ民族の限定を超えて多様な民族からなる広大な地域に及ぶ新しい支配の形態を志向した。この動きはそれまでの支配の形態と大きく異なるため、「アッバース革命」と呼ばれている。この革命により、アラブ民族と非アラブ民族の制度上の違いは縮小すると同時に、宗教としてのイスラームはアラブ民族を超えて広まり、イスラームが広範な地域に広がる世界宗教の性格を鮮明に帯びるようになった。アッバース帝国が新たに築いた首都のバグダードは人口100万人を超える世界第一の都市であり、経済的にも、広範な地域から物資と富が集中し、広大な地域に広がったイスラームの勢力範囲はもちろん、インドや中国からも医薬品を含めた奢侈品や文物が流入した[2]。8世紀ごろに成立が始まった『千夜一夜物語』(『アラビアン・ナイト』)に描かれるような華麗な豪奢の世界は、現実からかけ離れた夢幻の世界ではなかった。
この富を背景にしたアッバース朝の上層の階級は、支配地域に古代から存在した多様な宗教、学問、医学の伝統を活用した多元性を持つ文化的な後援活動を活発に行った。ことに、アッバース朝のカリフである、アル・マンスール(在位754-776)、ハルン・アル・ラシッド(在位786-809)、マムーン(在位 813-33)らは、非アラブ起源の学問、ことにギリシアの哲学や自然哲学の著作の翻訳を大規模な形で後援した。その理由は、もちろんカリフたち自身が学問を愛好し尊敬したという事情もあるが、より重要なことは、この時期に、ムタジリア(Mu’tazilia)と呼ばれる、イスラームの神学を理論化・体系化する知的運動が興隆し、そのために非アラブ・非イスラームの知をイスラーム内部に取り込んで広範な帝国の文化的な基盤にする必要が生じたためである。この動きは、もちろんイスラームの強化を目的としたが、排他的な性格よりも、他者を包含する性格を持つものであったため、非アラブ系の民族や非ムスリムとの共働が不可欠であった。ことに、当時のイスラームの大きな目標であった、ビザンティン帝国のギリシア正教や善悪二元論を唱えたマニ教との教理上の論争に勝利するための準備は、コーランや旧約・新約聖書などの宗教的なテキストだけでなく、それ以外の自然世界についての世俗の学問を用いる方向に向かった。宗教と自然哲学を結び付けて、より強力で説得力がある宗教の議論を作り上げるために、イスラーム世界はギリシアの自然哲学に向かうことになった。14世紀になっての記述ではあるが、傑出した歴史学者のイブン・ハルドゥーン(1332-1406)が『歴史序説』において、科学は特定の宗教集団に限られるものではなく、すべての宗教集団に属する人々が学ぶものであるという内容のことを述べているが、ある意味でこの考えに沿って、ムスリムだけでなく、ネストリウス派のキリスト教徒やユダヤ教徒も動員して、科学知識を増やすことが目標にされた。そして、このような宗教的な多様性の中で得られる世俗の科学的な議論こそが、イスラームが他の宗教を超えるための重要な手段であると考えられていた。
アッバース帝国の文化政策の中枢であったバグダードには「知恵の館」(バイト・アル・ヒクマ)と名付けられた図書館が設立されて、強力な知的拠点となった。カリフたちは優れた学者を発掘して各地に派遣し、手稿の書写、収集、そして翻訳を行った。ギリシア医学をはじめとする自然哲学の書物は、イスラーム勢力に征服されることになった各地のキリスト教の修道院などに保存されており、文化資源を共有する仕組みが歴史的に形成されていた。この条件に支えられて、アラブ・イスラーム文化におけるギリシア医学の手稿の発見、翻訳、注釈などは、驚異的に高度な水準に達することになった。現在の我々が知っているギリシアの医書は、そのほとんどがイスラーム文化において知られていたし、ギリシア語のオリジナルが残存せず、アラビア語への翻訳のみが残っている医書も数多くある。
このようなアッバース朝の多元的な医学の拠点としてしばしば語られてきたのが、ジュンディーシャープール(Gondēshāpūr)の地に栄えたとされる医学であるが、この問題については注意が必要であり、現在ではその実在は多くの学者によって否定されている。かつての説明では、ジュンディーシャープールはサーサーン朝の王によって4世紀にギリシア医学を含めたコスモポリタンな性格を持つ学院が設立された地であり、この地にネストリウス派のキリスト教徒やビザンティン帝国から追放されたギリシアの学者たちが居を構えていた。そこには病院も設立されて、大規模な医学研究と教育が行われていたという。しかし、ジュンディーシャープールでこのように壮麗な医学研究が行われていたことが最初に語られたのは13世紀であった。その実在を示唆する史料が1000年近くも存在しないのは奇妙な事態である。また、これを物語ったのは、おそらく、バグダードで代々のカリフの侍医となったネストリウス派のキリスト教徒であるバクティーシュー家のメンバーである。彼らが当時のバグダードの医学と医療の繁栄を参考にして、数世紀を遡って作った虚構であると解釈するのが適切だろう。この虚構のもとになった、小規模のキリスト教の修道院における医療や、ギリシア医学の書物の集積などはジュンディーシャープールやその周辺の土地に実在した可能性はあるし、サーサーン朝におけるコスモポリタンな学術の保護のパターンにも合っている現象である。その意味で、ジュンディーシャプールでの医学の繁栄は、史実ではないが、人々を信じさせることができた神話であると考えられる[3]。
アッバース朝期の翻訳家として、医学の領域で傑出しているのは、フナイン・イブン・イスハーク(d.873)である。フナインは、イラク南部出身のネストリウス派キリスト教徒であり、同地で勢力が強かったマニ教にも通じていたことが、アラブ・イスラーム世界の医学における翻訳運動の初期の特徴をよく示している。フナインは、その弟子とともに、膨大な量のギリシア語を中心とする医学書を多数アラビア語に翻訳した。ビザンティン帝国、シリア、イラク、エジプトなどの各地を旅行し、私家や修道院を訪ねて、所蔵されている手稿を書写した。その翻訳の手法は、フナイン自身が解説するように、それまでの逐語訳や音の移動を超えて高度に発展したものになり、アラビア語にギリシア自然哲学の語彙と概念を導入することになった。フナインとその弟子たちは、ガレノスの著作を120点以上、エフェソスのルーフスの著作を50点以上も翻訳し、アラビア語で読むことができるギリシア医学文献が爆発的に拡大した(図1)。フナインの少し後にバグダードで活躍したキリスト教の1つの教派に属するクスタ・イブン・ルカ(d.912)は、各地を旅行して医学をはじめとして、自然学、数学、天文学などの領域における著作を数多く執筆し、その中で残存するものは、彼の広範な知的興味と才能を示している。古典古代の医師の中でも特にガレノスが愛好されたことは、そもそもこの翻訳運動の目的が、イスラーム神学のための理論武装と繋がっていたことを思い起こせば首肯できる。臨床の観察と洞察に主眼を置いたヒポクラテスよりも、アリストテレスやプラトンの哲学を用いて理論体系を構築することをより強く志向したガレノスは、神学論争における優位と文化的な保護事業をめざすアッバース帝国の翻訳運動と同じ波長を持っていた。ガレノス自身の論争的な口調も、彼が愛好された原因の1つだったのかもしれない。
イスラーム医学の黄金時代

図2 フナイン・イブン・イスハークの眼科書より。 カイロ国立図書館
9世紀に本格化した翻訳運動はその後も継続されたが、10世紀の初頭には、ギリシア語などからアラビア語に翻訳された医学書はすでに膨大な量におよび、医学者たちは、アラブ・イスラーム世界独自の学術的な医学書を世に問うようになった。この動きは、特定の主題に関するモノグラフの執筆という形で始まった。フナイン自身も、眼科学の書物を執筆し、その後のアラブ・イスラーム世界が傑出した業績を残す領域の基礎を築いた(図2)。医学全体におよぶ優れた業績を挙げた学者の1人が、アル・ラージー(d.925 ラテン名ラーゼス)である。アル・ラージーは、ペルシア北部のライー(Rayy)で自然哲学、錬金術、音楽を学び、30歳でバグダードに移って医学を学んだ。ライーとバグダードの両市で病院の監督医の地位につき、医学を中心にして論理学、哲学、数学などについて約200点の書物を執筆した。伝統的な医学史の中では、『天然痘と麻疹について』という書物で、史上初めて天然痘と麻疹という2つの疾病を臨床的に区別する方法を示したことで名高い。このことが示唆するように、アル・ラージーは臨床的な観察力においても優れていたが、それ以上に、この書物は、天然痘の病理、診断、治療などの各側面の知識を総合するという、知的な総合運動の様子を示している。より重要な著作は、ライーの総督のマンスール・イブン・イシャク(d.914-15)に捧げられた『マンスールのための医学の書』である。同書は10巻からなり、1-6巻は理論的な側面の解説で、食餌、衛生、解剖、生理、一般病理、薬学がそれぞれの章で論じられ、7-10巻は実践的な側面で、診断、治療、個別の病理、外科が論じられている。この書物は、のちのアラブ・イスラーム世界の医師たちによって大いに利用されただけでなく、ラテン・キリスト教世界にも大きな影響を与えた。1175年ごろにイベリア半島で活躍した医師であるクレモナのジェラルドによってラテン語にも訳され、ことに、個別の病理を論じた第9巻は、頭部から足部までの病理を体の上部から順に論じており、高く評価された。この巻は、注釈をつけられて頻繁に写本され、17世紀に至っても出版されていた。ラテン語はもちろん、ビザンティン帝国の医師のためにギリシア語に訳され、ユダヤ人の医師のためにヘブライ語にも翻訳されている。
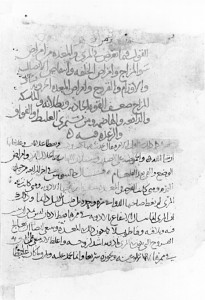
図3 アル・ラージー『医学の総合書』の写本より、消化器系疾患に関するノート。 アメリカ国立医学図書館
アル・ラージーのもう1つの重要な著作は、医学情報をのちに利用するために組織する新しい方法を示唆するものである。彼は、自らが参照した書物からノートをとり、その主題別に参考文献の該当箇所を抜き書きして自身の考察を加えたものを蓄積していた。これは、医学書が膨大なものになり、その中から必要とする情報や疑問点などを効率的に組織するための個人的な備忘録であると同時に、医学の情報検索システムの前身と考えることができる。記述の対象となっているテキストには、現在その存在がアル・ラージーのノートでしか知られていないものも多い。そのため、アル・ラージーの死後に、この備忘録は『医学の総合書』と題して出版された。これは、それ自体として膨大な書物であることや、組織・編集の点で欠陥があったが、大きな影響力を持った[4](図3)。
アル・ラージーの医学総合書を発展させ、より有用なものにしたのが、10世紀末に没したアル・マジューシー(ラテン名ハリー・アッバース)である。ハリー・アッバースは『医術の全体』を、イラクとペルシアの一部を支配した王のアブッド・アル・ダウワ(在位 949-83)に献呈した。アル・ラージーの『マンスールのための医学の書』と同様に、理論と実践の2部に分かれ、それぞれが10章で構成されている。記述は、アル・ラージーのものよりもコンパクトであって筆写・流通がたやすく、同時により総合的なものであるため、非常に高く評価された。ヨーロッパにおいても、前章で触れたコンスタンティヌス・アフリカヌスがまずラテン語に訳した最初の書物の1冊である。

図4 イブン・シーナ『医学典範』の写本より。 イェール大学医学部図書館
医学を総合した著作の中で、中世最大の大著と呼べるものを残したのが、ペルシア出身で、法学や哲学にも通じたイブン・シーナ(d.1037 ラテン名アヴィケンナ)である。イブン・シーナは医学を中心に250点以上の書物を執筆したが、その中でも傑作は『医学典範』と呼ばれる5巻本の書物である(図4)。本書は、アル・ラージーやアル・マジューシーのような理論と実践への二分法の配列を批判して、医学が自然哲学の中の一領域であって、理論はもちろん個別の実践においても自然哲学の原理が反映されていることが鮮明になるような構成をとった。原理の基盤はアリストテレスの3つの生命力の議論であり、また、ガレノスが体系化した四体液説の説明であった。この原理に従ってのみ、疾病を理解して診断や治療を行うことができることが理解できるように構成されていた。また、ガレノスの著作の中に散在している、様々な個別の主題に関する議論や結論を抜き出して、それらをイブン・シーナの体系のしかるべき部分に配した。
その結果、『典範』が提示したのは、1つのシステムとして理論的な基盤を持ち、個別の実践が確固とした理論的な説明を持つような医学の体系であった。四元素や四体液の考え、生殖、腐敗などについての原理的な議論が、特定の病への薬の調合、外科、産科などの各論と鮮明に結び付けられた。この書物が、高度な医学を学ぶ医学生の教科書として優越したものであったこと、そして、個別の現象の理論的な解釈は賛成・反対の双方の議論を生み出すものであった。この著作は、イスラーム世界で広範に利用されたのはもちろん、中世ヨーロッパの医学においてもラテン語に訳されて標準的な教科書となり、1527年に出版された新ラテン語訳は、30回も再刊された。注釈においては、ラテン語、ヘブライ語はもちろん、各国語での注釈を合計すると、まさに数百の注釈が作られ、医学の歴史全体において、これほど詳細な研究の対象になった書物はないだろうといわれている。

図5 イスラーム医学における妊婦の解剖図。マンスール・イブン・イリャース (fl. ca. 1390)『人体の解剖』の写本 より。 アメリカ国立医学図書館
フナイン、アル・ラージー、イブン・シーナらは、いずれもアッバース帝国の拠点であったペルシアを基盤にして活躍した医師であったが、他の地域でも医学者たちが活躍した。イベリア半島のザラハーウィ(fl.c.940)は、30の論考を含む書物の中で、産科学、子供の養育、調理、心理学、スペインの自然誌など、他の書物で論じられることが少ない主題を取り上げていた。また、ギリシア医学を論理的に再構成した総合書を書くだけでなく、イスラーム世界の独自な貢献も数多く上げていた。著名な例では、シリア出身でのちにエジプトで活躍した医師で多彩な領域での著作を残しているイブン・アル・ナフィース(d.1288)が、イブン・シーナの『医学典範』の解剖学の記述についての注釈の中で、実際に解剖を行って、血液が右心室と左心室の間の穴を通って移動すると考えたガレノスの説を否定した(図5)。この発見は、17世紀のイギリスでウィリアム・ハーヴィーが発見した血液循環のモデルには至らなかったが、イスラーム世界の医学をガレノスの盲従と考えてはいけないことを示唆している。薬学においても、薬材が採取された範囲は広大な地域にまたがり、様々な地域の植物、動物、鉱物について、多言語の名称をアラビア語に統一し、利用の際に重要な統一的な秤量のシステムを作るなどの発展と洗練が進んだ。紀元1世紀のローマ帝国で活躍したディオスコリデスの自然誌が850点ほどの薬材を記しているのに対して、アンダルーシアのイブン・アル・バイタル(d.1248)が記述した書物は、3000点以上の事物を記録している。
アラブ・イスラーム世界が生み出した医学書の写本は、当時の水準を考えると、まさに膨大なものである。現在のトルコ国内だけで、アラビア語を中心に、ペルシア語、トルコ語の医学写本で現存しているものを合計すると、400人の著者、1000点の書物、その写本が合計で5000点にのぼるという[5]。この活発と生産の背景には、751年に中国の唐帝国とアッバース帝国がタラス河畔で戦闘した折に伝えられた、紙の生産の技術も存在した。中世のイスラーム世界が、征服した地に古代以来継続した文化遺産を活用すると同時に、アッバース帝国の文化政策に推し進められて、水準が高い医学知識の生産と流通のメカニズムを作り上げたことがうかがえる。