「名もなきケア責任」のジェンダー不均衡をめぐって始まった平山亮さんと山根純佳さんの往復書簡。長きにわたった連載もついに最終回、今回は前回の対談を受け、お二人による対談後記をお届けします。
日々の実践を通じて不平等な構造は変えられるし、私たちは協働のパートナーになれる。外出自粛に伴い要介護高齢者や子どもの生(life)を支えるさまざまなケアが「家庭内」に集約されてしまう現在。「ケアの危機」を乗り越え、よりよい社会に向け歩みだすために。[編集部]
対談では、ケア責任のジェンダー不均衡が続く現状について、ケアの与え手への「承認」や受け手からの「信頼」というテーマで意見を交わすことができました。私たちは論点のいくつかについてはようやく合意し、別のいくつかについてはいまだに合意していないのですが、他方、対談のなかでは表立って語られてはいなかったものの、私たちが共有していた問題意識がありました。それは、「この現状を変えるには、個人としての男たちが変わってもらわないといけないし、私たちにはそれを主張し続ける必要がある」という問題意識です。
男性によるケアへのコミットメントの少なさ(あるいは難しさ)については、構造的な制約がその原因として語られてきました。例えば、「男は働いて一人前」という価値観に押されつつ、長時間労働を前提とした就労体制のもとで働くことで、家庭にいられる時間が少なくなること。それから、対談でも話題にのぼった(不)承認の問題、すなわち、男にはケアが期待されず、やっても認めてもらえないこと。それらが、男性がコミットしない/できないことの原因としてよく取り沙汰されています。
もちろん私たちも、こういう制約が「ない」と考えてはいません。しかしながら、こうした説明に違和感を覚えずにいられないのも事実です。その違和感とは、ジェンダー論における男性は、どうしてこうも受け身の存在なのか、というものです。言い換えれば、この現状が維持されていることに対する男性の能動的関与=エージェンシーは、どうしてここまで問われずにいるのか、と。「妻が認めてくれないから、家事をする意欲が削がれる」もそうですが、ケアにコミットしない/できない男性が語られるとき、彼らは常に周囲にコントロールされ翻弄されるだけの、まったき受け身の存在として想定されているように思うのです。
男性の受動性を前提とした不平等の正当化
実のところ、男性をひたすら受け身の存在として想定すること、他方で、不平等が続くことに対する女性の責任(「妻が認めてくれないからだ」のように)を強調することは、ジェンダー不平等を正当化(legitimize)するために繰り返し使われてきたレトリックです。それは、性暴力をめぐる言説を思い起こせば、よくわかるでしょう。性暴力の被害者には圧倒的に女性が多いわけですが、それは、女性が男性の欲望を喚起させたことや、拒否の意思を明確に示さなかったことに帰責されてきました。男性は女性に刺激されたら欲望を抑えられず、また、女性に明確に意思を示してもらわない限りは察することもできず、要するに、ひたすら女性に「○○され」「××してもらう」しかない存在とされる。男性のこのような受動性を所与の前提にしているからこそ、被害者の落ち度や女性の自衛の必要性が「なるほど、そうだよね」になってしまうのです。
上の「妻が認めてくれないから」でも、男性が家事を行うかどうかは、女性からの評価の単なる関数のように扱われています。妻がいくら言っても、あれやこれや理由をつけてケア責任から逃げ続け(られ)る男性、その意味で、妻がどう思っているかなんてどこ吹く風の男性など、いくらでもいる。にもかかわらず、それはいつの間にか忘れ去られ、女性の言うことにいちいち左右される男性像ばかりが、なぜか「あるある」にされてしまうのです(こちらがどう思っていようと、あるいはこちらが言葉を尽くしていくら説明しようと、全然変わってくれない男の姿を目の当たりにしている女性からしたら、そんなふうに自分たちの言うことにいちいち左右されてくれたらどんなによいか、と思っていることでしょう)。
結果、男性がケアにコミットしないのは、男性のやり方を認めない女性の偏狭さに帰属されることになります。要するに、女たちは自分の首を絞めているのだ、と。そして、声高に主張せず、男たちを萎縮させないことが、スマートな女のふるまいのように語られる。既に不利益を被っている側に、それを変える責任も、変えられなかった責任も、丸ごと帰属すること――まさにそれこそが、不平等の構造を「しかたない」ものに見せるためのレトリックになっているにもかかわらず。
「構造によるプレッシャー」を論じることの、ジェンダー非対称な効果
フェミニズムが、性役割の概念や「構造によるプレッシャー」といった考え方を採用したのは、女性が経験する不利益の責任を、女性自身に帰属させるこのレトリックに対抗するためだった、といえるでしょう。たとえ女性が、自ら不利な立場に身を置こうとしているように見えたとしても、そこには彼女たちをそのように仕向ける社会の力が働いているのだ、と。そういう社会の力を可視化することで、不平等な状況に対して女性を過剰に責任主体化しようとするレトリックに対抗しようとしたのだ、と。
だとすれば、社会の力によるこの説明を、男性の場合にも安易に同様に当てはめることは、危険きわまりないといえます。男性が社会の力に規制され、いかにそれにコントロールされているかを強調することは、男性をまったき受け身の存在に見せることで不平等の構造を正当化する、これまで通りのレトリックとぴったり重なるからです。
「構造を問題にする」と言いながら、制度や規範による圧力で男性の現状を説明しようとする一部の男性(性)研究が、フェミニストの不信を買うのはそのためでしょう。その説明自体が、不平等の構造を維持する男性の能動的関与を消去し、彼らを免責させ続けてきた当の論理とまったく同じであることに、そして、その論理でこれまで何がもたらされてきたかに、あまりに無頓着だからです。
「問題なのは構造なんだから」で行われる「再生産実践」
ケア責任のジェンダー不均衡も含め、現在も続く不平等をいかに変えるかを考える上で不可欠であり、にもかかわらずほとんど手つかずのままに残っているのは、この「男性の能動的関与=エージェンシーをいかに問うか」という問題ではないでしょうか。
「女のすなることを、男もしてみむとするなり」とばかり、男性たちは「構造によるプレッシャー」という考え方に飛びつきました。しかし、その「プレッシャー」を言挙げし、「縛られ奪われ苦悩する僕ら」を描き出す情熱に比べたら、構造に相対する男性のエージェンシーを検証することへの関心の薄さは明らかです。それは、過剰に責任主体化されることへの抵抗として「プレッシャー」を可視化してきた女性学ですら、不平等の維持に加担する女性のエージェンシーにメスを入れてきたこととは対照的です。
「個人を問題にしてもしかたがない」「問題なのは構造だ」は、男性についてに限らずしばしば聞かれる主張ですが、構造は個人の行動を決定するわけではありません。私たちは、私たちにとって使える資源や、社会的に良しとされている考え方といった所与の条件(構造)を参照しながら、「じゃあ、自分はここでどう動こうか」と日々選択を行っています。これこそまさに、山根さんが『なぜ女性はケア労働をするのか』(勁草書房、2010年)で定式化したエージェンシー、すなわち「構造に対する解釈にもとづく能動的実践」にほかなりません。その意味で、個人は単なる受け身の存在ではないのです。
そもそも構造は、私たちの行動とは独立して存在しているわけではありません。不平等な構造は、私たちが日常的にしてきたこと・していること、とりわけ、山根さんのいうところの「再生産実践」の集積によって成り立っています。「再生産実践」とは、既にある構造を「好都合」なものとして解釈し、その構造をよりどころに他者とやりとりし(交渉実践)、結果として現状維持をもたらすような実践のことです。
だとすれば、「ケアにコミットできないのは構造のせい」「構造が変わってくれなければ、コミットしたくてもできない」と女たちに向かって説くことは、それ自体「再生産実践」になるでしょう。「ケア=女性の責任」とする構造を参照すれば、男性がケアにコミットしなくてもよい理由はいくらでも簡単に見つかります。その構造を論拠に「僕らがいかにケアにコミットできないか」を「証明」すること、そしてそれを女性に納得させようとすることは、構造をよりどころにした交渉実践にほかなりません。
事実、それによって黙らされた女性たちは少なくなく、その意味で交渉が「成功」に終わることは稀ではなかったでしょう。というのも女性自身、構造による制約は身に染みてわかっており、それをむげに否定することなどできなかったからです。構造に制約される痛みをよく知る女性に、構造を論拠としてぶつけるという効果的な手口でもって反論や抵抗を抑えつつ、男性はここでもまた、構造に対するまったき受け身の存在として再構築される。翻って、その構造を成り立たせる男性の能動的実践(エージェンシー)は、またもや有耶無耶にされていく。「変わりたくても変われない僕ら」を正当化し、ケア責任の不均衡がなかなか是正されない現状を「それじゃあ、この現状もしかたないかもね」に仕立て上げるという巧妙な「再生産実践」が、ここでも行われています。
構造のもとでの「変動実践」こそ男たちに求められている
率直に言って「構造のせいでケアにコミットできない」説明はもう十分、もっと言えばそろそろうんざり、というのが女たちの本音でしょう。構造を踏まえた上でもっと積極的に論じ、また実際に行ってもらいたいと女たちが男たちに思っているのは、「再生産実践」ではないほうの能動的実践、すなわち「変動実践」についてでしょう。「変動実践」とは、現状の「しかたなさ」を訴えて相手を納得させるためではなく、その現状を自ら変えるために周囲の他者とやりとりする変化志向の交渉実践によるものです。
男性がフェミニズムにもっと学ぶべきなのは、この変動実践の理論化と実践のしかたについてではないでしょうか。なぜならフェミニズムこそ、この変動実践がいかに可能になるかにずっと取り組んできたからです。フェミニズムは、女性たちを制約する構造を分節化だけしてきたわけではありません。そのような制約のなかで、その制約の理不尽さを「見える化」し、反駁するための言説を探し出して駆使し、ときに自らの手で作り上げながら、交渉できる限りの他者との交渉を試みて、自身を取り巻く状況を少しずつ変えてきました。同じことを、男性もできないはずはありません。
もちろん、男性が「構造によるプレッシャー」を言語化し続けてきたのは、取り組むべき対象(あるいは討つべき敵)を明確にするためだ、と捉えることもできるかもしれません。でも、それにしては敵を知るため(だけ)の期間が長過ぎやしないか、とも思えます。そして、自分たちに変わることを訴える女性に対峙するためにその知識に恃み、その意図はどうあれ、結果的に「再生産実践」にコミットしてしまっている向きも少なくないのは前に述べた通りです。
幸いなことに、いかに「変動実践」を試みることができるかについて、男たちが今すぐにでも学ぶための教材は、あちこちに見つかります。山根さんの『なぜ女性はケア労働をするのか』は、女性だけでなく男性についても、変化志向の交渉実践がいかに行われうるか・行いうるかを理論的にも実証的にも示したものです。また、大野祥子さんの『「家族する」男性たち』(東京大学出版会、2016年)は、構造的制約のなかで自身の生き方を変えるために、個人としての男性ができることに焦点を当てたプロジェクトの成果です。「変えたくても変えられない」とひたすら嘆いて終わらなくても、男性には変化志向の交渉実践がいかに可能になるかを学ぶためのリソースが、既に用意されているのです。
社会を変えるために、女と男が手を取り合えるとき
構造を語るときに、自身を単なる受け身の存在とせずに、その構造を参照し、いかに振る舞うかを選ぶアクターとしての自分を語ること。構造を持ち出して「変わりたくても変われない僕ら」を女性相手に語ること、それ自体がエージェンシーを駆使した「再生産実践」にほかならないことを理解すること。その上で、男性による「変動実践」がどのようにして可能になるのかを検討し、実際に行ってみること。そうやって「個人としての男性がいかに変化を起こせるか」に取り組むことが、ケア責任のジェンダー不均衡を是正するためにいま最も求められている課題です。
「構造によるプレッシャー」を言挙げするだけでなく、その構造に対する自身のエージェンシーを男性が直視して初めて、男たちはジェンダー論に関して「女のすなることを、男もしてみ」たことになるはずです。そしてそのとき男性は女性にとって、現状を変えるための社会的協働のパートナーに、遅まきながら、ようやくなりうるのではないでしょうか。
平山さんが言及してくださったように、私は女性・男性の「エージェンシー」による性別分業の再生産や変動について論じてきました。この社会では、男性であるか、女性であるかによって、利用できる資源が異なって配分されており、私たちはその利用可能な資源をつかって生きています。たとえば「経済的資源」の所有や「稼得者」になるための機会がない女性たちにとって「ケア能力」という資源を用いて「ケアラー」になることは能動的実践である、と。こうしたジェンダー化された資源配分の説明は、対談でとりあげたように男性が「ケアをしないこと」を正当化するものでもあります。たとえば男性は「ケア」をしなくても承認されるが、女性はケアラーであることによってその社会的な承認を得ることができます。だから男性が「ケアをしないこと」もこの構造の制約のせいだ、と。女性が働くという選択が可能になっても、夫よりも妻のほうが、長い育休の取得を承認されやすい、だから妻のケア責任が大きくなるのは当然だ、と。
しかし、これは男性が性別分業という構造の「犠牲者」であるということを意味しません。ニーズを察知したりそれに応える方法を思案するというSAにかかわることは、男性だからできない、ということはありません。ではなぜ家庭ではそれをしようとしない男性が多いのか。「仕事に支障がでるから」「仕事のほうが楽だから」「妻がやってるから」これらはすべて「自分が変わりたくない」ことと同義です。つまり男性たちは「ケアしない男性」を能動的に再生産しているのです。この状況を変えるのは「変動」に向けた男性のエージェンシーにかかっています。今回は、コロナ禍における家族のケア、というテーマに絡めてこの問題を論じて、対談後記としたいと思います。
なぜ女性はケアするのか、再考
前回の対談で私は、他者のニーズを察知したり思案したりしても、個人としての「利得」があるわけではない、と繰り返しました。このような言い方にはケアには「やりがい」がある、愛着から好きでやってるんだろうという反論もあるかもしれません。もちろん察知したり思案したり、それに沿ったケアを提供するという活動について、判断に困ったときには誰かに相談でき、その「試行錯誤」でやっているケアの内容について誰かから批判されることもなく、疲れたときには誰か交代してくれる人がいる、そのうえで本人が感謝の意を表明してくれたり、活動の成果が目にみえてわかる、といった条件が整えば、それは「やりがいのある活動」と言えるかもしれません。でも家庭内のケアにおいて、そんな条件が整うわけがありません。ケアラーたちは「やりがい」がなくても、子どもや要介護高齢者のケアをつづけています。
そして今、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校休園、外出自粛のなかで、家事、身体のケア、心のケア、すべてを「家庭 home」のなかで供給することが求められています。子どもや要介護高齢者の世話をしているケアラーは、「非日常」を生きるためのSA=察知・思案にも追われることになりました。家庭での「正しい過ごし方」とは何か、いつまでテレビを見させていてもいいのか、どのような子どものニーズを尊重すればよいのか、1日中フルタイムのSA(察知・思案)をしている方も多いでしょう。ここで家庭に集積された責任を果たしたからといって、誰かがその活動を評価してくれるわけではありません。オンライン上には家庭内で実践可能な子どもの運動や図画工作、親がすべき子どもの「心のケア」が並べられていますが、子どもの性格も、子どもにかけられる時間も、教育にかけられる資源も、きょうだいの数も、親の数も、家族によって違うなかで、「こうすれば乗り切れる」などというマニュアルなど存在しません。特に学校休校のあいだ、教育までもがノーマニュアルで家庭に委ねられるという「キャパ超え」の状況を生きているわけです。「正解」のわからない不確実性のまっただ中で、親のSA=察知・思案の責任が増幅しています。
女性はSAを好きでやっているのか
さて、こうした状況のなかで女性たちに「SAをやめる」という選択肢はあるでしょうか。もちろん、ゲームやテレビに子どもを預ければ解放されますが、1日のなかの一定の時間にすぎません。毎度の食事の用意だけでなく、家のなかにいる子どものようすを察知したり思案したりしないで子どもの存在を無視して過ごすことは困難です。小さい子どもであれば親のところに寄ってきますし、少し大きくなり手が離れた子でも何をしているか確認し、トラブルや危険があれば何か手を打たなければいけません。保育園や学校、さらには友人関係というネットワークから切り離されれば、親は24時間責任から逃れることができません。同様にデイサービスが休業になり自宅にいる高齢者の生を支える察知・思案、介護の負担も大きくなっています。
しかしケアラーたちは家族の「義務」であるがゆえに、増幅したSAをおこなっているわけではありません。SAをつづけている、つづけざるをえないのは、それをやめれば、生存のために他者のケアを必要としている存在をネグレクトすることになるからです。それゆえ、ケアラーは「個」としての時間を確保することが難しい状況にあります。現在、在宅勤務をしている男性たちの多くも、そのニーズの大きさ、そして逃れがたさをはじめて実感しているでしょう。一方で、子どものニーズに応えきれないという状況を、暴力によって対処しようとする親もいるなかで、子どもが親以外の「信頼」の対象とつながれる、SOSを出せる支援が必要です。
では、こうした状況のなかで、家族のなかのあるメンバー(女性)だけSAをつづけることでその人が得る「利得」はあるでしょうか。同じ在宅勤務をしている夫婦で、妻のほうが子どもの呼びかけに応じ、食事を考え、テレビやゲームの時間を調整して他のアクティビティをさせようとすれば、妻の仕事がすすまないのは当然です(くわえて、子どもはたいてい、丁寧に対応してくれる親のほうに寄っていくので、人気のないほうの親は子どものニーズに気付かずにすみます)。もちろん妻が仕事をしていない場合には「わかりやすい不利益」はないかもしれません。しかし、感染予防・拡大リスクと子どものニーズを天秤にかけて最適な行動とそれを実現するための方法を思案し、1日の生活リズムから1週間21食分の食事を考え、夫が在宅の場合には子どもが夫の仕事を妨げないように促す方法を思案しつづける……こうした切れ目のない思案の連続のなかで「やりがい」を見いだせる場面があったとしても(子どもが皿を洗ってくれた!)、それが妻個人の利益であるとはいえないでしょう。そればかりか、夫が家族内の責務を他人事とみなし、妻のマネジメントの「成否」を評価するようなふるまいをする場合には、妻は精神的プレッシャーにさらされることになります。このような状況で「子どもの世話をするのは女性」という不均衡な責任の配分によって女性が得る利得は、ありません。それでも社会から閉ざされた家族という領域のなかで、子どもや高齢者に向けてSAをおこなうこと、「呼びかけ」によって生じる責務からおりることができないのです。
このようにいわば「やむをえず」SA(察知・思案)をしつづけることは、私が女性の「エージェンシー」概念によって論じた利用可能な資源を用いた「能動的実践」でも、選択可能な選択肢からより大きい利得を得るための「合理的選択」ともいえません。以前ここで書いたように、他者のニーズに応えようとすることは、自らの利益を犠牲にしたり、また自分ひとりでは対処や解決が困難な状況を抱えるという意味で「脆弱」な位置に自らを置くことでもあります。そしてケアラーはその脆弱性を乗り越えるための「つながり」「相互依存」を必要としているのです。そして今、この相互依存関係も家族のなかでしか取り結ぶことができない状況にあります。
社会の機能が停止するような非常事態において家庭にさまざまな機能が集約されてしまう、その責任が女性だけに課されれば限界はきます。突然の一斉休校にしても、変化に伴う調整の負担がまったく考慮の外に置かれ、家庭の責任に委ねられました。また家庭内だけでなく、学童や病院や高齢者施設といった社会のケア機能を担う機関へも同様で、利用者のニーズへの応答だけでなく、物質的・人的資源の調達、リスク防止に向けたマネジメントが各機関の責任に委ねられ、その多くが女性であるケアワーカーに負担が集中しています。従来とまったく異なる条件のもとで、脆弱性にさらされる人々の生活や生命を守ることが求められるという意味で、「ケアの危機」に直面しているといえます。
もちろん、平常時であってもニーズの高い乳児の世話や認知症高齢者の介護は非常事態といえます。「限界を超えている」という悲鳴に対し、「好きで子ども産んだんだろ」「好きで専業主婦になったんだろ」という発言は暴力でしかありません。たとえ私たちは子どもを持つことや専業主婦になることを能動的に選んだのだとしても、状況によって増幅するケアの責務に応えることを選んだわけではないからです。
ケアラーである女性はSAをやめることもできないし、SAによって得る利益があるわけではなくとも、その責任から降りることができない状況に置かれています。このような家庭のなかで次の「手」をもっているのは男性です。家庭内にどれだけのニーズがあるのかを認知し、それに応えることを自分の責務として認知する。たとえ誰も評価してくれなくても、自分の仕事を後回しにしてでも、男性が他者のニーズに応える思案を分有してくれなければ、性別分業は変わっていきません。不確実性のなかで誰もが耐えている今だからこそ、男性が家庭のなかのケアニーズに応えうる主体になることで、「ケアの危機」が乗り越えられることを祈っています。
本連載は加筆修正のうえ、書籍化予定です。お楽しみに![編集部]
 【プロフィール】平山 亮(ひらやま・りょう) 1979年生。2005年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了、2011年オレゴン州立大学大学院博士課程修了、Ph.D.(Human Development and Family Studies)。東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム研究員を経て、現在、大阪市立大学大学院文学研究科准教授。著書に『迫りくる「息子介護」の時代』(共著、光文社新書、2014年)『きょうだいリスク』(共著、朝日新書、2016年)。気鋭の「息子介護」研究者として、講演、メディア出演多数。『介護する息子たち 男性性の死角とケアのジェンダー分析』のたちよみはこちら→「序章」「あとがき」
【プロフィール】平山 亮(ひらやま・りょう) 1979年生。2005年東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了、2011年オレゴン州立大学大学院博士課程修了、Ph.D.(Human Development and Family Studies)。東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム研究員を経て、現在、大阪市立大学大学院文学研究科准教授。著書に『迫りくる「息子介護」の時代』(共著、光文社新書、2014年)『きょうだいリスク』(共著、朝日新書、2016年)。気鋭の「息子介護」研究者として、講演、メディア出演多数。『介護する息子たち 男性性の死角とケアのジェンダー分析』のたちよみはこちら→「序章」「あとがき」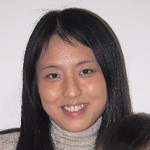 【プロフィール】山根純佳(やまね・すみか) 1976年生。東京大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了し、博士(社会学)取得。2010年山形大学人文学部講師、同准教授を経て、2015年より実践女子大学人間社会学部准教授。著書に、『なぜ女性はケア労働をするのか 性別分業の再生産を超えて』(勁草書房、2010年)、『産む産まないは女の権利か フェミニズムとリベラリズム』(勁草書房、2004年)、『現代の経済思想』(共著、勁草書房、2014年)、『正義・ジェンダー・家族』(共訳、岩波書店、2013年)など多数。
【プロフィール】山根純佳(やまね・すみか) 1976年生。東京大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了し、博士(社会学)取得。2010年山形大学人文学部講師、同准教授を経て、2015年より実践女子大学人間社会学部准教授。著書に、『なぜ女性はケア労働をするのか 性別分業の再生産を超えて』(勁草書房、2010年)、『産む産まないは女の権利か フェミニズムとリベラリズム』(勁草書房、2004年)、『現代の経済思想』(共著、勁草書房、2014年)、『正義・ジェンダー・家族』(共訳、岩波書店、2013年)など多数。》》山根純佳&平山亮往復書簡【「名もなき家事」の、その先へ】バックナンバー《《
vol.01 見えないケア責任を語る言葉を紡ぐために from 平山 亮
vol.02 女性に求められてきたマネジメント責任 from 山根純佳
vol.03 SAには「先立つもの」が要る――「お気持ち」「お人柄」で語られるケアが覆い隠すこと from 平山 亮
vol.04 〈感知・思案〉の分有に向けて――「資源はどうして必要か」再考 from 山根純佳
vol.05 思案・調整の分有と、分有のための思案・調整――足並みを揃えるための負担をめぐって from 平山 亮
vol.06 なぜ男性はつながれないのか――「関係調整」のジェンダー非対称性を再考する from 山根純佳
vol.07 SAの分有に向けて――ケアの「協働」の可能性 from 山根純佳
vol.08 Sentient activityは(どのように)分けられるのか――構造、自己、信頼の3題噺 from 平山亮
vol.09 ジェンダー平等化の選択肢とケアにおける「信頼」 from 山根純佳
vol.10 SA概念で何が見えるか(前編)――「男は察知も思案も調整も下手」で「やろうと思ってもできない」のか from 平山亮
vol.11 SA概念で何が見えるか(後編)――“ゆるされざる”「信頼」の対象と“正しい”思案のしかたをめぐって from 平山亮
vol.12 [対談]社会はケアをどのように分有し、支えるべきなのか/山根純佳・平山亮
vol.13(最終回) [対談後記]連載の結びにかえて/平山亮・山根純佳

