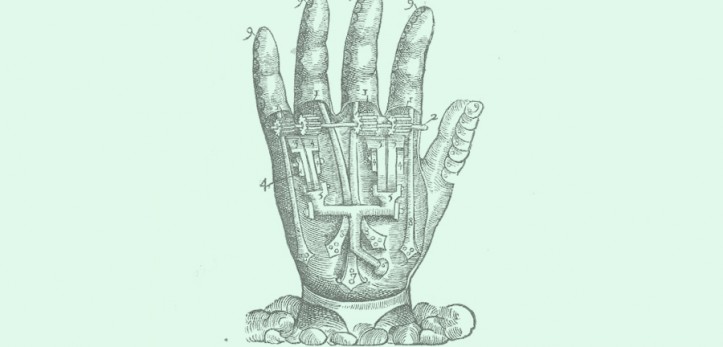
医学史とはどんな学問か
第2章 中世ヨーロッパにおける医学・疾病・身体
キリスト教と聖なる癒し
イスラム圏などから移入された発展した医学が大学を基盤にして広まっていた時期に、キリスト教による病気の解釈と対応も発展した。かつての医学史は科学的な医学とキリスト教を対立する二つの力として捉えており、例えば医学史家のシンガーは、20世紀の初頭に行われた講演で、ガレノスの死後の解剖学と生理学の凋落を「進行性麻痺」とまで呼び、その理由をキリスト教の教義と占星術に求めている。この著しく偏った説明の基盤にある科学と宗教の二項対立論は歴史的には的を外しており、前節でみた医学が劇的に進展していたのと同じ時期に、キリスト教に基づく病気と身体の理解も大きく進展していたという事実に合わない。中期・後期の中世は、異教の学問的な医学に基づく疾病の理解と対応、そしてキリスト教に基づく病気と身体の理解と対応の双方が進展した時代であった。言葉を換えると、中世ヨーロッパの<自然の医療>と<聖なる癒し>は、対立的に考えるべきではなく、相互に補いながら共存していたのである。
そのため、かつて、教会と医学の対立を示すと考えられていた事例は、現在では別の解釈が施されている。たとえば、1299年に教皇ボニファティウス8世が大勅書を出して「人体を切り裂く行為」を禁止したとされる行為は、実際には医学的な人体解剖を禁止したのではなく、ドイツやイギリスの王や貴族が異国で死んだときに身体を各部分に切断して保存できる状態にして輸送することに対する禁止であった。人体の解剖が大学に導入されたときに、教会は現在の我々の多くと似たような態度をとり、そのこと自体を好意的に見ていたわけではないが、人体解剖を必要なことであると考え、適当な手続きを踏んで解剖される死体が死刑を受けた刑死体であることと、解剖の後に適切な埋葬をされるかぎり行ってよいという態度を表明した。あるいは、教会が修道士の医療を禁止したことは、営利的な医療によって修道士の宗教的な義務が乱されることがないようにするためであり、聖職者の品位を保つために宗教的な生活を守るための規則であった。
カトリック教会の活発な宗教拡大の影響をうけて、ギリシア医学とは異なった原理をもつ聖なる癒しが発達した。その中でも特筆に値するのが、地域ごとに発展した聖人の癒しである。聖なる癒しは初期中世から存在し、キリストの聖遺物などが祀られている教会や、聖人と関係が深い社などを直接訪問し、そこで聖遺物に触れて社で一晩眠るなどの直接的な身体の接触により疾病が癒されて障碍が回復するというシナリオであった。これらの聖なる癒しは、ギリシアのアスクレピオスの神殿での治療と類似しているし、福音書で描かれるイエスの癒しとも重なっている。また、イエスの癒しと同様に、現代の医学でも簡単に治せるわけではない慢性の疾患や障碍に対応して用いられており、約半数は肢体不自由や麻痺などの身体障碍、1割から2割が視覚・聴覚の障碍、そして1割程度が精神障碍である。14世紀以降には、このような聖なる癒しが地域的な限定を超えて行われるようになった。直接の身体の接触がなくても、夢にキリストや聖人が登場するという形や、遠距離を超えて祈りをささげることという手段を通じて、キリストや聖人とヴァーチャルな接触をして治療されることが可能になった。直接の身体の接触への信仰はもちろん残ったが、それを求めるために巡礼しなくてもよくなった。このように聖なる医療が可動的になり市場が広がると、それぞれの疾病ごとに聖人を専門分化することができるようになる。ペストは聖ロック、眼病は聖ルチア、ハンセン病は聖アエギウスという形である。後期中世の聖なる癒しは、その「市場」が広がり、疾病ごとに聖なる医療の分化が進むという変化を経験した。
聖なる癒しの発想は、世俗権力である国王の聖なる力という方向にも発展した。国王は、教会と潜在的な緊張をはらんでいたもう一つの力であり、イギリスとフランスでは、王が疾病を癒す聖なる力を持つという信仰が現れた。病気に苦しむ患者は王を訪ね、王が患部に触れて十字を切り、コインを入れた水で手を洗うと病気が治るという治療である。のちに、結核の一種である<るいれき>に効くとされた。ちなみに、るいれきは緩和することが多く、王が癒す力を信じる根拠は比較的多かったとされている。王の聖なる力の医療は、もともとはゲルマン民族の王たちが持っていた聖性の表現であったが、中世に再び取り上げられて発展したのは、王が自らの権力を示す政治的なメッセージであったと歴史家たちは解釈している。その権力は、教皇と対抗した場合でもあるし、別の血統の王家や貴族との対立を踏まえた場合でもよい。緊張や危機に陥った王が、癒す特別な力を誇示することでその正統性を主張しようとして作られた聖なる治療であった。ヨーロッパで最後のこの治療を行った王が、フランス革命後に帰ってきた復古ブルボン朝のシャルル10世であったことは、王の聖なる治療が持つ権力の正統性の根拠を示す性格を象徴している。
文化と社会の中の疾病――ペスト・ハンセン病・拒食症
ギリシア起源でイスラム圏経由の医学と、キリスト教などの聖なる癒し、そして学問の外で営まれた医療が共存したように、それぞれの疾病ごとに異なった医療と病気の経験が形成されたことを明らかにできる。そのような疾病の中から、ペスト、ハンセン病、そして「拒食症」という三つの疾病を選んで、それぞれの疾病・病気についてあらわれた重要な動きを解説しよう。これらは、a) 現実の疾病が新たに現れた場合、b) 以前から存在した疾病に新たな注目と対応がされた場合、c) 中世の人々は疾病であるとは考えていなかったが、現在の医学的・社会的な視点からみると疾病だと考えられる場合に対応する。
a) ペスト(黒死病)
ペストは、ペスト菌の感染によって起きる疾病であり、ネズミなどのげっ歯類に寄生するノミがヒトからヒトへとペスト菌を媒介することによって起きる。また、ペストに感染したヒトの唾液などに含まれたペスト菌を吸い込むことによっても起きる。この疾病は、中世だけでなく、世界史上で最も大規模な疾病の流行を中世のヨーロッパで引き起こした。1347年にはじまって1353年に終息した「黒死病」と呼ばれる大流行である [2]。この流行は、おそらく中央アジアに始まり、1346年に黒海の東岸に到達して、1347年にコンスタンチノープル、シチリアなどから地中海沿岸のヨーロッパに侵入した。そこからヨーロッパを時計方向に回り、1352年にキエフ、53年にモスクワに到着するという経路をたどった。のちにこの流行は「黒死病」と呼ばれることとなり、史上最大の被害を出した感染症である。歴史学者による死者の推計には幅があるが、ヨーロッパの人口の三分の一から半分以上であっただろうと考えられている。この割合は、広島に投下された原爆が出した死者と住民の割合と同程度であり、それが全ヨーロッパにわたって展開したと想像すると、黒死病の被害を生々しくイメージできるだろう。
黒死病は空前絶後の大惨事であり、カトリック教会は、神が人類に与えた処罰であると解釈し、教会では罪を悔い改めて神に許しを乞う行事が行われ、人々は深い悔悛の念を表現した。のちに人々はその大流行を振り返って「死の舞踏」の主題で絵画などを描き、この世の生のはかなさと人間の無力さに深い思いが込められた。悔悛の念は、信者自らの身体に誇示するかのように暴力を振るう形もとり、鞭打ち苦行団と呼ばれる14世紀の初頭から存在していた宗教運動がドイツ圏の各地で燃え上がり、街から街へと移動して広場などの公共の空間で行列しては我が身を鞭打った。また、この暴力が、他者を対象とする事例も頻発した。最も身近にいるキリスト教を信じない異教徒はユダヤ人たちであり、各地でユダヤ人を追放する動きが見られ、フランクフルト、マインツ、ケルン、ブリュッセルなどの多くの都市でではユダヤ人たちが虐殺され、ジュネーヴでは小屋に追い込んで焼き殺す残虐行為が見られた。黒死病に際して、深い宗教性の表明と並行して、自己と他者へのけばけばしい暴力が見られた。これが、どの程度までキリスト教やヨーロッパの特殊性によるのか、それとも人間の精神や社会が大惨事に直面したときに陥る共通の傾向なのかについては、歴史学者や社会学者で考え方が異なっている。しかし、同じ時期にペストに見舞われて大きな被害を受けたイスラム圏と比較すると、イスラム圏では、鞭打ち苦行団や他者の迫害・虐殺の事例は現れず、むしろ宿命論的にこの被害を受け入れる傾向が強かったとする研究書も存在することは付言しておく。
黒死病の後、ヨーロッパとその周辺の諸地域は、数十年に一度ペストが襲来することが数世紀にわたって継続した。その中で、イタリアの諸都市を中心にして、世俗の権力による新しい対応法が現れて拡散した。都市の内部と外部における人々の移動、特にペストに罹っている人々の移動を制限する隔離と検疫である。ヴェネツィアにおいては、黒死病とそれに続いて起きたペストの流行に対応するために、1446年に常設の衛生委員会が設立され、ペストが疑われる人物が市内に入るのを禁じる規則が作られた。多くのイタリアの都市においても類似の規則が作られ、ペストの患者を隔離するための病院が建設された。また、14世紀の後半から、現在の検疫のメカニズムと同じ原理である、ペストが流行している地域からの人々と商品などが市内に入る場合には、40日間市外に留め置くシステムが各地に作られた。このような隔離と検疫の発想は、当時の医学の体液論に基づいた疾病の理解とは適合しなかったし、患者と接触する行為に癒しの基本が存在すると考えている教会の理念とも合わなかった。これは16世紀の事例であるが、人々が集まることでペストの感染が広がるのを恐れたフィレンツェの市参事会が教会でのミサを禁止した時に、カトリック教会が市参事会を破門するという事態もあった。ペストに対する隔離検疫は、この時期にラテン・キリスト教世界で発展していた世俗の権力の影響であり、この要素は、近代以降の医療と公衆衛生、そして人々の疾病の経験と理解に大きな力を持つことになる。そして、この隔離政策の基本的なアイデアを提供したのは、当時のラテン・キリスト教世界で広く行われていたハンセン病患者の共同体からの追放と隔離であった。