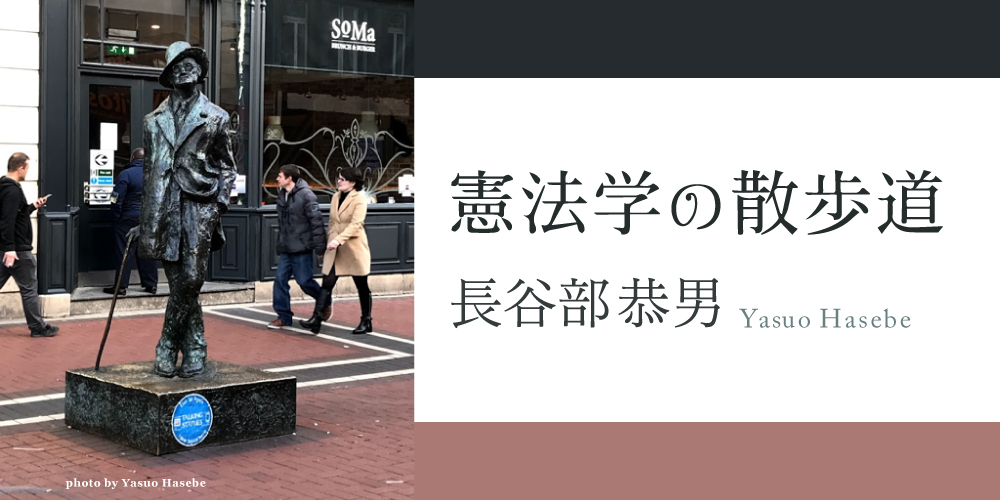「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
エトムント・フッサールは現象学の祖である。彼は判断停止(epoché)による現象学的還元という手段を用いて意識の構造を分析した。
人の意識には志向性(Intentionalität)がある。庭の梅の木を見る、ショスタコヴィチの交響曲第5番を聴く、軽やかなピノ・ノワールを味わう、フッサールはフライブルク大学の教授だったと考える。対象を見たり、感じたり、考えたりする。そのとき人は意識している。
意識の内容は「梅の木」、「第5番」、「ピノ・ノワール」「フッサール」であり、そうした意味(Sinn)を持つ。人は意味を通じて対象を意識する。フッサールは、意識の内容をノエマ(noema)と呼んだ(複数形はnoemata)。人はノエマを通じて対象を意識する。
人は、通常、自分の意識の内容と対象とを区別することはない。単に庭の梅の木を見るのであって、「梅の木」という自分の意識内容を通じて、現に庭に生えている梅の木を見ているとは考えない。
そこで判断停止という手続が必要となる。庭に生えている梅の木が現に存在するか否かについての判断を停止する。梅の木が実在するかという問題をいわば括弧に括ることで、自分の意識の内容である「梅の木」の存在が浮かび上がる。庭の梅の木と意識の内容である「梅の木」は別物である。
しかし、括弧に括ろうとしても括ることのできないものがある。「梅の木」を意識している自分自身である。
同じことは、交響曲第5番を聴いている自分、ピノ・ノワールを味わっている自分、フッサールはフライブルク大学の教授だったと考えている自分についても当てはまる。意識している自分自身の存在は疑いを容れる余地がない。意識作用なるものが成り立つための必然的な前提である。
フッサールはこの事態を指して、必然的な前提である自我自身は超越論的だと述べることがある*1。カントの超越論的認識論にヒントを得た言い方であろう。カントが、アプリオリな認識作用がそもそも成り立つための条件が何かを考察したのと同様、フッサールは、意識作用が可能であるための条件が何かを考察した。
しかし、フッサールは、われわれにとって認識可能なのはノエマとしての「梅の木」だけであって、庭の梅の木そのものではないと考えているわけではなさそうである。カントのように現象界と本体界を区別して、前者のみが認識可能だと考えているわけではない。
彼は、庭の梅の木と意識の内容である「梅の木」とは異なると言う。庭の梅の木は、丸焼けになったり、化学的要素に解体されたりすることがある。しかし、意識された意味内容としての「梅の木」は丸焼けになったり、化学的要素に解体されたりすることはない*2。庭の梅の木は実在する。それは丸焼けになったり、化学的要素に分解されたりする。
もちろん、意識作用の必然的前提である自分自身と同等の疑いようのない実在として庭の梅の木が存在するというわけではない。フッサールは、われわれを取り巻く世界の存在の絶対的確実性を証明してくれるものはないと言う。世界をどれだけ経験し、観察したからと言って、そうした証明を考え出すことなどできない*3。それでも、梅の木は存在するとわれわれは考える。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道