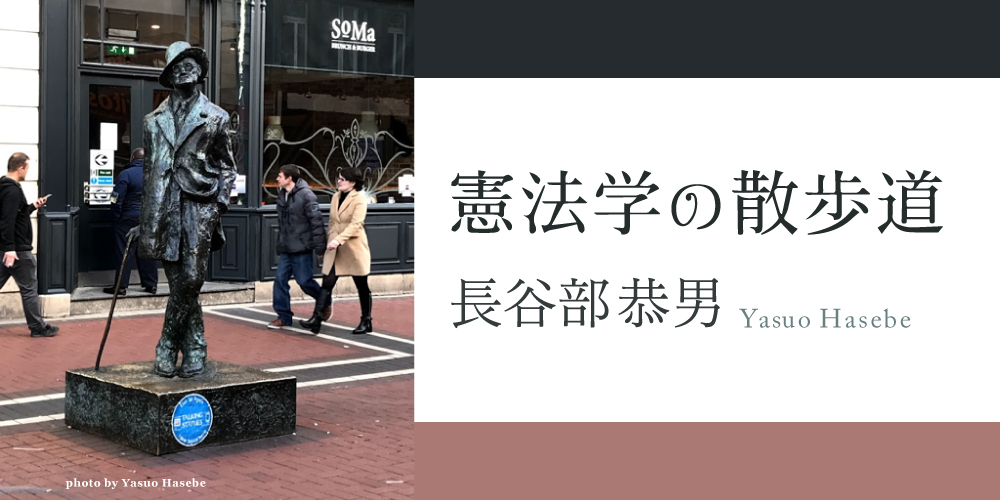「憲法学の散歩道」単行本化第3弾! 書き下ろし1編を加えて『思惟と対話と憲法と――憲法学の散歩道3』、2025年10月15日発売です。みなさま、どうぞお手にとってください。[編集部]
憲法学、もう少し広くとって法律学の世界では、内的か外的かが、いろいろな局面で問われる*1。H.L.A.ハートは、規範一般について、内的視点と外的視点とを区別した*2。
規範に則した行動には、内的側面と外的側面とがある。
毎週末に、新宿のデパートに出かける習慣のある人がいるとしよう。彼女の行動には一定の規則性──毎週末に新宿のデパートに出かけるという規則性──がある。しかし、ある週末、別の用事があって新宿のデパートに出かけなかったとしても、誰もそれを咎め立てはしないであろうし、彼女自身も、それを後悔することはないであろうか。
他方、彼女が前方の信号が赤であるにもかかわらず横断歩道を渡ったとすると、彼女はそんなことはすべきではなかったと批判する人が出てくるであろうし、彼女自身も、うっかりしていたと反省するのではなかろうか(道路交通法など自分とは関係ないという人もいるかも知れないが)。
赤信号では横断歩道を渡らないという彼女の行動(不作為)には、たいていはそう行動するという外的な規則性があるだけではなく、その規則を行動に対する評価規準とみなす内的側面が伴っている。これに対して、毎週末に新宿のデパートに出かけるという行動にあるのは、外的側面だけである。
ハートがここで行っているのは、社会学的な分析である。法律を典型とする規範には、内的側面と外的側面とがある。単なる習慣であれば、外的側面だけがあって、内的側面はない。内的側面に着目しない限り、規範と習慣とを区別することはできない。
ハートは、内的側面から行動を評価すべきだと主張しているわけではないし、特定の規範が行動の評価規準として適切だと主張しているわけでもない。人は普通、規範に関しては、それにもとづいて行動を評価するものだ、それが通常の人々の行動のあり方だと指摘しているだけである。
内的側面からの行動の評価にあたって人々が行っている判断が正しいか否かは、人が普通、規範に則して行動を評価するものかどうかとは別の問題である。正しい(ことがあり得る)か否かについて、ハートは何も言っていない。権威という概念を軸としてこの問題を分析したのは、ハートの弟子であるジョゼフ・ラズである。ラズの議論については、ここでは触れない*3。
法律論についても、内的か外的かが問題とされることがある。
つづきは、単行本『思惟と対話と憲法と』でごらんください。
 遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
遠い昔の学説との対話を楽しみつつ、いつしか「自意識」が揺さぶられる世界に迷い込む。憲法学の本道を外れ、気の向くまま杣道へ。
2025年10月15日発売
長谷部恭男 著 『思惟と対話と憲法と』
四六判上製・216頁 本体価格3200円(税込3520円)
ISBN:978-4-326-45147-0 →[書誌情報]
【内容紹介】 書き下ろし1篇を加えて、勁草書房編集部webサイトでの好評連載エッセイ「憲法学の散歩道」の書籍化第3弾。心身の健康を保つ散歩同様、憲法学にも散歩がなにより。デカルト、シュミット、グロティウス、フィリッパ・フット、ソクラテス、マッキンタイア、フッサール、ゲルバー、イェリネク等々を対話相手の道連れにそろそろと。
「憲法学の散歩道」連載第20回までの書籍化第1弾はこちら⇒『神と自然と憲法と』
「憲法学の散歩道」連載第32回までの書籍化第2弾はこちら⇒『理性と歴史と憲法と』
連載はこちら》》》憲法学の散歩道