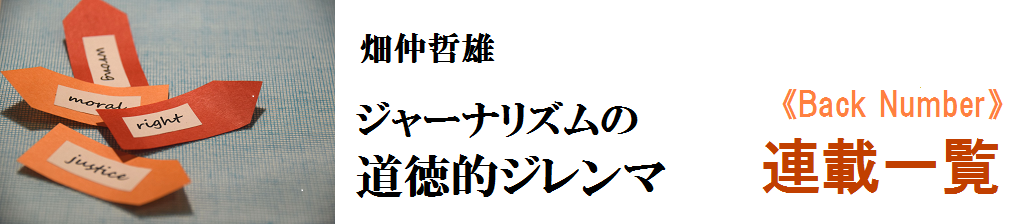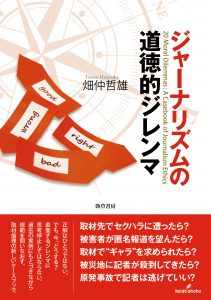 取材先でセクハラに遭ったら?
取材先でセクハラに遭ったら?
被害者が匿名報道を望んだら?
取材で“ギャラ”を求められたら?
被災地に記者が殺到してきたら?
原発事故で記者は逃げていい? etc.
現場経験も豊富な著者が20のケースを取り上げ、報道倫理を実例にもとづいて具体的に考える、新しいケースブック! 避難訓練していなければ緊急時に避難できない。思考訓練していなければ、一瞬の判断を求められる取材現場で向きあうジレンマで思考停止してしまう。連載未収録のケースも追加し、2018年8月末刊行。
〈たちよみ〉はこちらから→〈「ねらいと使い方」「目次」「CASE:001」「あとがき」(pdfファイルへのリンク)〉
【ネット書店で見る】
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
畑仲哲雄 著 『ジャーナリズムの道徳的ジレンマ』
A5判並製・256頁 本体価格2300円(税込2484円)
ISBN:978-4-326-60307-7 →[書誌情報]
【内容紹介】 ニュース報道やメディアに対する批判や不満は高まる一方。だが、議論の交通整理は十分ではない。「同僚が取材先でセクハラ被害に遭ったら」「被災地に殺到する取材陣を追い返すべきか」「被害者が匿名報道を望むとき」「取材謝礼を要求されたら」など、現実の取材現場で関係者を悩ませた難問を具体的なケースに沿って丁寧に検討する。
今回は、通常のスタイルから離れてこれまでの連載を振り返りつつ、ジャーナリズムの現場が抱える難しさをふまえた連載のねらいを、著者・畑仲哲雄さんが率直に語ります。[編集部]
今回は特別に、〈思考実験〉→〈異論対論〉→〈まとめと解説〉→〈実際の事例〉→〈思考の道具箱〉といういつもの構成とは異なり、この連載「ジャーナリズムの道徳的ジレンマ」の〈問い〉や〈狙い〉について述べてみます。
●正しさの複数性と多元性
この連載は2016年4月にスタートして、これまでに計18のジレンマを取り上げました。いずれも、過去に起こった実際の事例をベースにしています。なかでも連載初回の「ハゲワシと少女」は、教科書に載るほど有名な写真が照射した典型的なジレンマ問題です。
少し詳しく見てみましょう。
飢餓に倒れた子供が、いまにも大型の鳥に食べられようとしている――そんな瞬間を切り取った1枚の報道写真が、世界に大きな論争を巻き起こしました。1993年、アフリカのスーダンで撮影されたというこの写真は、ジャーナリズムの世界で「優れた作品」として絶賛されました。その一方、撮影したジャーナリストに対しては、「撮影よりも人命救助ではないか」という非難の声が殺到しました。

Photo credit: takacsi75 via Visualhunt / CC BY
「ハゲワシと少女」のような悩ましい問題に、ただひとつの「正解」などありません。なにをなすべきか。なにが正しい行いなのか。それは時代によって、地域によって、あるいは文化によって異なります。同じ時代・地域・文化圏内に暮らす人びとの間でも、社会階層や年齢、職業などによって正しさをめぐる基準が異なることは、多くの人が経験しています。
●ジャーナリストの専門職性
ジャーナリストたちには固有の職業規範があり、新聞社や放送局などメディア企業にも業界固有の倫理があります。それは、じぶんたちの存在理由を市民社会に向かって説明するものといっていいでしょう。なぜなら、ジャーナリストという職業は、国家資格の医師や法律家とは異なり、じぶんたちの専門職的な性質や社会的な使命をじぶんたちで説明しなければならないからです。
しかし、それらが市民社会に理解されているわけではありません。それどころか、ジャーナリズムの作法が、いわゆる「世間」の掟や素朴な道徳感情と相容れないことは珍しくありませんでした。
それでも、マスメディアやジャーナリストは挫けることなく、報道の大切さを読者や視聴者に繰り返していねいに説明して理解を求めていくべきなのでしょうか。はたして、それは原理的に可能なことなのでしょうか。
こんにちの日本で、ジャーナリズム倫理の根幹をなしているのは、日本新聞協会が1946年に公表した「新聞倫理綱領」です。これを出発点に、大手の新聞各社や放送局が企業ごとの行動基準やルールを作ってきました。
「新聞倫理綱領」がつくられた時代は太平洋戦争の敗戦直後、いわゆる占領期で、当時の新聞経営者たちは連合国総司令部(GHQ/SCAP)の民間情報教育局(CIE)から“再教育”を受けていました。このため日本の新聞倫理綱領はアメリカ型のジャーナリズム観が反映されました。それだけではありません。戦後日本の報道メディアは、アメリカの主流新聞社や放送局を“お手本”として仰いできました。とりわけ『ニューヨークタイムズ』や『ワシントンポスト』などの高級紙は「あこがれ」や「信仰」の対象だったのではないでしょうか。
●自由主義のジャーナリズム
ところで、アメリカのジャーナリズムは、古典的自由主義が色濃く反映されていることが規範理論の研究者たちによって論じられてきました。キーワードをひとつ挙げれば、「思想の自由市場」があります。どんな思想が正しいのかを知るには、それを自由な市場で競争させればよくて、間違った思想は駆逐され、正しい思想が選択されるだろう――そんな考え方から、「言論の自由」の正当性が導き出されてきました。
アメリカの主流ジャーナリズムの倫理の中心には、「表現の自由」に至高の価値を見いだそうとする太い幹があります。それは、イギリスからの自由を求めて独立した建国の精神に沿うもので、アメリカ社会の基層をなしていると言っていいでしょう。

Photo via VisualHunt
占領下に日本の新聞界を指導した民間情報教育局(CIE)が作成した「プレスコード」にも、「ニュースの筋は事実に即し、編集上の意見は避けるべし」と記されました。CIEの狙いは、新聞各社の言論を操作することでしたが、文言としてはアメリカのジャーナリズム倫理にかなう表現といえるでしょう。
アメリカでは、ジャーナリストは取材対象に働きかけてはならず、冷徹な観察者に徹するべきだという倫理が主流メディアのなかで確立され、それに同意する日本のジャーナリストも少なくありません。ニュースでは事実だけを伝えるべきで、恣意的に世論を誘導してはならないという規範は今日も説得力をもっています。
●「ハゲワシと少女」が問う道徳
そんな論理からすれば、「ハゲワシと少女」を撮影したジャーナリストは、なんら責められることはありません。仮に、ハゲワシが少女を食べはじめたとしても、その事実を撮影して伝えるのが正しい行為となります。〈CASE 01〉の「まとめと解説」で紹介した通り、コロンビア大学教授のステファン・アイザックスは「残酷に聞こえるかもしれないが、それがジャーナリストの役割だ」と論じました。
じっさい、「ハゲワシと少女」を撮影した南アフリカのケビン・カーターは、アメリカのジャーナリストにとって最高の栄誉、ピュリツァー賞を受賞しましたが、その翌月、オランダの街角で自動車に排ガスを引き込んで命を絶ちました。世界中から非難されたことが自殺の原因であったのかどうかはわかりませんが、彼が深く苦悩していたのは関係者の話から確認されています。
カーターが撮影した写真を難じた人のなかには、アメリカの新聞社や新聞の読者も多数います。カーターを責める意見はラジオやテレビでも報じられていました。つまりアメリカ国内においても、主流メディアの倫理がすべてのメディアに受容され、支持されているわけではなかったのです。
この一件で、アイザックスがいうような主流ジャーナリズムの倫理が崩壊したわけではありません。しかし、一流紙のジャーナリストや高名な学者たちが形成してきた職業倫理は、ときにふつうの人には「残酷に聞こえる」ことをはっきり示しました。つまり、主流ジャーナリズムの職業倫理には、読者や一般市民の間で共有されている道徳感情と相容れないことが起こりうるし、ジャーナリストたちに心理的トラウマを植え付けかねないということです。
●エシックスとモラル
ここで、この連載で使用している言葉について、簡単な整理をしておきましょう。
この連載では、倫理と道徳を厳密に区別したり、使い分けたりしていません。強いていえば、道徳という言葉には、有徳な人になることに重きが置かれ、倫理は理論的な一貫性を意識して用いてきました。こうした区別は、日本で生まれ育ったわたしの実感にすぎません。
エシックス(倫理)やモラル(道徳)などの言葉は、ギリシャ・ローマの時代から論じられ、アリストテレスの倫理学では実践を重んじられていましたし、今日も道徳哲学や徳倫理学では道徳が学問の対象となっています。
倫理や道徳を扱うには、それなりの知識を要しますが、この連載では学術用語としての厳密性はいったんわきにおいて、両者を実質的には同じものとして通俗的に捉えてきました。
ところで、戦後の日本では「道徳」という言葉が放つ独特の響きにも触れておく必要があります。ひとことで言うと、戦時下の「教育勅語」のような軍国教育が連想されるのです。戦後生まれの政治家が「教育勅語には良いことも書かれていた」などと公言する時代でもあるだけに注意が必要かもしれません。
ジャーナリストは特定の政治的イデオロギーから等しく距離をとるべきで、バイアスのない事実だけを提供していれば市民社会は正しい選択をする――そんな理屈がマスメディアの内側には沈潜しています。「政治的に公平であること」を求める放送法の条文も、こうした傾向に棹さしているといえるでしょう。
●グッドニュースとバッドニュース
しかし、ジャーナリストは客観的な事実だけを公平中立に伝えることはできるのでしょうか。
どのような時代・地域・文化圏にあっても、善と悪を区別する軸、すなわちモーレス(習律)やノーム(規範)があります。ジャーナリストたちがニュースを報じる際、読者や視聴者の反応を事前に予測しています。犯罪や災害はバッドニュース、美談や成功譚はグッドニュースに分類しているはずです。
すべてのしがらみから逃れて、頭の先から足の先までジャーナリスト以外のアイデンティティをもたない人はいません。問題は、取材するジャーナリストたちの行為や決断が、市民社会の素朴な道徳感情と相容れない場面があることです。
ジャーナリストたちも、多くの場合、地域コミュニティの一員です。町内会の役員を引き受けたり、子育てに手を焼いたり、夏祭りで子供たちに駄菓子を配ったり、地元のスポーツチームを応援したり、ボランティア活動をしたり……。そんな隣人としての自己認識が、日々のニュース活動の源だという記者は珍しくありません。
それゆえ、ジャーナリストはときに職業倫理と市民道徳との間で股裂きに遭うのです。だからこそ、道徳的な視点から目をそらさず、むしろ積極的に考えてみようじゃないか、というのがこの連載の狙いです。
●一兵卒としてのジャーナリスト
ところが、現実のジャーナリストたちは、内規やルールブックに準じて瞬時に決断を下すことが求められます。判断できないときは上司や経営者に判断を仰ぐ。それが優れた組織ジャーナリストとしての所作なのでしょう。
編集現場は“戦場”です。極論すれば、記者もデスクも部長も、みないつも締め切り時間に追われ、「抜いた」「抜かれた」の闘いにせき立てられます。彼ら彼女らに熟考する時間はどれだけあるでしょう。道徳的なジレンマに直面するたび、頭が真っ白になったり、泣き崩れてペンも握れなくなったりしているようでは仕事になりません。だれもが道徳的な悩みを後回しにしているのではないかと思われます。

Photo credit: Julia Manzerova via VisualHunt.com / CC BY-ND
しかし、最前線のジャーナリストたちには、じぶんが直面している難問を考えたり、分かち合ったりする場があるようには見えません。それが日本のジャーナリズムを停滞させる原因になっていないでしょうか。
そんなわたしの問題意識にたいして、ある新聞人はこんな意見をくれました。「取材者が道徳的なジレンマに直面したときの問題を考えるのは、管理職以上の仕事であって、新人記者は基本ルールや内規を身につけるのが先決です」。しかし、それが行きすぎれば、従順な“兵士”を量産することにつながります。
●ケースブックとして
なるほど、社内の取材マニュアルを改訂する役目は管理職にあるのでしょう。でも、取材をめぐる道徳的な難問を考える資格は、ベテラン記者だけでなく、若手記者にも平等に与えられるべきです。むしろ取材現場から遠ざかった管理職より、現場の取材者にこそ必要だ、というのがわたしの考えです。
この連載は、取材現場で日々格闘する最前線の記者や、今後取材の現場に出て行く予備軍を意識して執筆してきました。むろん、デスクや部長など中間管理職の人たちを除外しているわけではありません。彼ら彼女らにも有効に使ってもらいたいと思っています。ジャーナリスト教育が盛んなアメリカではケースブックが作られることが珍しくありませんが、日本では同種の本はほとんど見かけないからです。
連載記事には、ひとつの主題を示す見出しをつけました。しかし「実際の事例」には、いろんな論点が含まれています。各記事のタイトルの後ろに、論点となるようなキーワードを付けてみました。
〈CASE 01〉最高の写真? 最低の撮影者?:[人命尊重][南北問題][記者の功名心][バッシング][危険地取材]
〈CASE 02〉人質解放のため報道腕章を警察に貸すべきか:[人命尊重][捜査協力][犯人の主張][記者の良心][隣人としての記者][地方紙][全国メディア][空撮ヘリ]
〈CASE 03〉その「オフレコ」は守るべきか、破るべきか:[オフレコ][記者懇][基地問題][沖縄ジャーナリズム][差別][失言報道][日米安保][全国メディア][記者の罪悪感]
〈CASE 04〉ジャーナリストと社会運動の距離感:[社会運動][地域医療][記者の良心][読者座談会][地域紙][ヒエラルキー]
〈CASE 05〉戦場ジャーナリスト、君死にたまふことなかれ:[危険地取材][戦争報道][フリーランス][記者の家族・遺族][自己責任論]
〈CASE 06〉組織ジャーナリストに「表現の自由」はあるか:[メディアの公式見解][記者の自律][記者の良心][記者会見の主宰者][編集権][立ちレク・囲み][吊し上げ]
〈CASE 07〉報道の定義、説明してくれませんか?:[記者クラブ][劇場型政治][政党の報道][行政の広報][報道の定義]
〈CASE 08〉原発事故、メディア経営者の覚悟と責任:[危険地取材][記者の避難][自己責任論][記者の罪悪感][ニュースの逆効果][ヒエラルキー][コミュニティ放送]
〈CASE 09〉小切手ジャーナリズムとニュースの値段:[有料の取材][記者会見の主宰者][取材謝礼][情報の売買][パパラッチ][メディアスクラム][著名人]
〈CASE 10〉取材謝礼のグレーゾーン:[有料の取材][取材謝礼][情報の売買][やらせ]ギャラ][ビジネス][著名人]
〈CASE 11〉メディアスクラムという名の人災:[マスゴミ][報道被害][プライバシー][視聴率][ニュースバリュー]
〈CASE 12〉取材先からゲラのチェックを求められたら:[表現の事前確認][編集権限][検閲][出版差し止め][専門的な知識]
〈CASE 13〉被害者の実名・匿名の判断は誰がする?:[実名原則][匿名報道主義][報道被害][メディア規制][死者の名誉][プライバシー][匿名社会][遺族の要望][断罪報道]
〈CASE 14〉世間に制裁される加害者家族をどう報じる:[加害者][家族・遺族][世間][制裁][容疑者][断罪報道][ネット炎上]
〈CASE 15〉「忘れられる権利」か、ネット上での記事公開か:[検索サイト][削除依頼][ニュースサイト][ソーシャルメディア][プライバシー][スニペット][アクセス権][マグショット]
〈CASE 16〉経営破綻を報じる時宜と大義:[破綻報道][倒産の引き金][パニック][取り付け騒ぎ][流言][ニュースの逆効果]
〈CASE 17〉犯人の主張を報道すれば犯罪の手助けになるか:[犯人の主張][差別][ゲリラ][捜査協力][金嬉老事件][記者座談会][グリコ森永事件]
〈CASE 18〉新聞の「編集権」はだれのものか:[編集権][地域紙][ヒエラルキー][NPOとの協働][社会運動]
たとえば、〈CASE 17〉は「金嬉老事件」をベースに検討しました。中心的な課題は「犯人の主張」ですが、事件の背景には在日朝鮮人に対する差別の問題があります。〈CASE 14〉で取り上げた加害者家族の問題を考える際には、村八分などに象徴される「世間」の問題も絡んでいます。ジャーナリストたちは、所属先企業の報道マニュアルを身につけてさえいればいい、というわけにはいきません。
わたしたちが考えるべき「ジャーナリズムの道徳的ジレンマ」は、まだたくさんあります。今後は不定期の掲載になりますが、皆さまからのご意見・ご提案も参考にしながら書き続けます。
* * *
わたしからのお願いが2点あります。
【1】「この事件も道徳的に悩ましいぞ」という情報を教えてください。
【2】記事を用いて研修やワークショップを開催したい方がおられましたら、運営に協力したいと思いますので、遠慮なくご連絡ください。
連絡先は以下です
〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 龍谷大学瀬田キャンパス
社会学部 畑仲哲雄研究室
メールアドレス hatanaka.tetsuo@gmail.com
[担当者の中〆] 大きな災害などがあると「常日頃の避難訓練が大事」とさまざまな場面で実感します。思考実験のような「ジレンマ」との格闘は迂遠に感じられそうですが、ジャーナリズム現場の避難訓練かもしれないと思っています。
》》》バックナンバー《《《
〈CASE 18〉新聞の「編集権」はだれのものか
〈CASE 17〉犯人の主張を報道すれば犯罪の手助けになるか
〈CASE 16〉経営破綻を報じる時宜と大義
〈CASE 15〉「忘れられる権利」か、ネット上での記事公開か
〈CASE 14〉世間に制裁される加害者家族をどう報じる?
これまでの連載一覧》》》