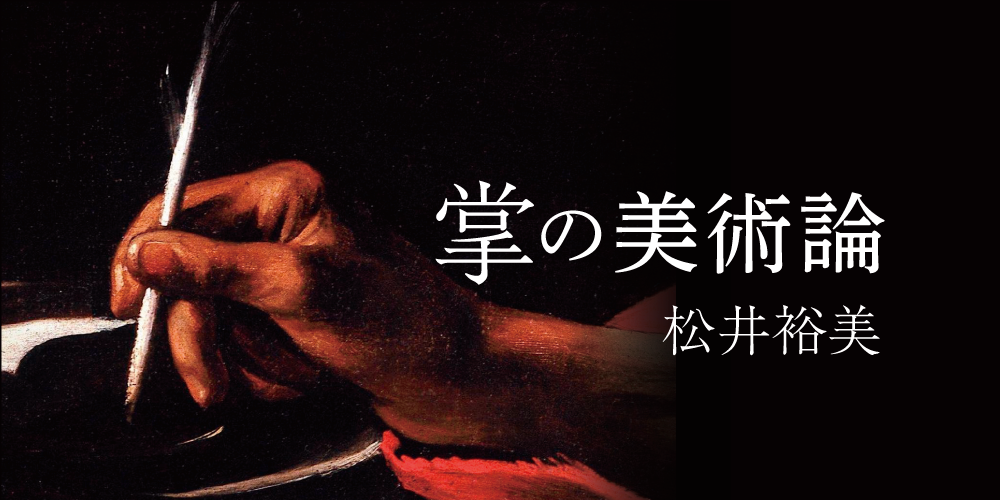ユートピアの作り方
あなたがユートピアの設計者なら、何から作り始めるだろうか。老いも死も苦痛もない世界の構想。貧困も差別もないシステムの構築。労働すら娯楽の一部であるような安らかで楽しい毎日。それに加えて胸踊るようなドラマだって用意されている。大いに結構だ。
だがあなたが設計者であるからには、図面を引かなければならない。土地の区画が決まったら、耐久性のある素材で建築物を築く。心安らぐ、あるいは胸踊る景色を生み出すために、本物の木と花を植える。ワクワクするような岩山は、安全面を考えれば人工的な素材で作るのが一番だが、見た目は本格的にしよう。岩山を険しく見せたいけれど、実際に鋭い角のあるものを使えば危険だ。子供が登ろうとして、いつその柔らかい掌や膝を擦りむいてしまうかもしれない。だから代わりに古くから絵画に用いられている陰影法を用いて、ちょっとした目騙し的要素を、岩山を模した塊に入れてやれば良い。喉が渇いたらいつでも潤せるよう、そこかしこに泉を作ろう。けれど衛生面を考えれば、泉はやはり人工的なものに限る。なんなら、注文があればすぐまっさらなコップに飲み物を入れて出すようなスタンドにしてしまおう。それから、安全性や衛生、食事などのサプライを維持するような労働も、ある程度必要になる。
そうするとユートピアは、だんだんと現実の世界に似てくる。しかしそれは現実の世界そのものであってはならない。現実とはいつでも危険で偶発的で不衛生で不幸で不都合な何かを孕んでいるからだ。現実的な問題を持ち込まないようにするためには、現実の世界の模造にとどまる必要がある。かくして、私たちがよく知っているディズニーランドが出来上がる。
フランスの文化史学者ルイ・マランは、1970年代にフロリダのディズニーランドを訪れ、彼が「退廃のユートピア」と呼ぶこの場のうちに、さまざまな記号により構成された現実世界の偽装された姿を見た。一方には本物の自然や機材と、対価によって商品を手に入れる資本主義経済があり、他方には紛い物の自然世界や機械文明と、入り口で手に入れることができる偽物の紙幣(当時ディズニーランドで使用されていた、園内でしか使用できない通貨)がある。マランはまたそこに、現実社会のシミュレーションも見出した。一方には古き良き世界への憧れ(フロンティアランド)があり、他方にはいまだ見ぬ世界への憧れがある。後者はマランによれば、未開拓の自然(アドベンチャーランド)と科学技術により可能にされる未来(トゥモローランド)という、ベクトルの異なるエリアとして、ディズニーランドでは体現されている。そして「アメリカ大通り」の行き着く先として、それらすべてをまとめつつ、まさにそれら複数のエリアへと人々を送り出す役割を担うのが、シンデレラ城のあるファンタジーランドなのである*1。
マランがこのユートピアを「退廃」と言うのは、それが第一に、現実によく似た紛い物の世界で繰り広げられる儀礼の内部に訪問者たちを取り入れるからだ。そこでは、帝国主義や資本主義といった現実のイデオロギーが、諸々のイメージを生み出す発生器として機能している。だが第二に、この「退廃」したユートピアは、彼らに現実の世界が抱える問題を忘れさせる。それだけではない。このユートピアは、現実世界を構造的に支える諸々のイデオロギーを肯定するよう仕向ける装置となっている。ディズニーランドの訪問者は、それぞれが舞台に上がる演者になるのであり、ユートピアの住人の一人としてその生活を楽しむ役を演じ続けるために、物語の筋書きをその身のうちに引き受けている。
記号論に依拠するマランの小難しい議論を踏まえなくても、このユートピアが一体何をどのように忘れさせているのかを知りたければ、2017年に上映された映画『フロリダ・プロジェクト』を見ると良いだろう。上映当時には日本でも話題を攫ったショーン・ベイカー監督によるこの映画では、ユートピアには入ることが許されない境遇にいる子供たちの視点から、その周囲に広がる生活と景色が捉えられていた。ディズニーランドの舞台に上がる人々は、一見すれば舞台に入り遊ぶことを許されない人々の生活と切り離されているようでいながら、そこには搾取する側とされる側がいる社会構造があり、両者の間に残酷な連続性がある。この連続性は普段はユートピアを囲う垣根に阻まれ見ることができない。しかしその垣根の外で貧困のうちに暮らす子供たちは、遊びを通して、過酷な現実もまやかしのフィクションもすべて、彼らの世界を構成するものとして取り入れていく。彼らはこうして、ユートピアと現実世界の境界線を脅かし、ユートピアが現実世界と結ぶ密やかな連続性を、映画を見る者の視線に晒す存在となるのである。
さて、ユートピア設計者としてのあなたは腕組みをして考える。不都合な部分だけ隠蔽しながら現実を理想化した世界を思い描くことが問題含みだというなら、はじめから既存の現実世界には存在しない、意味と歴史に欠けた、抽象的な現実を構築すれば良い。日系アメリカ人の彫刻家イサム・ノグチの構想に基づく札幌のモエレ沼公園は、そうして作られたユートピアだ。原色で彩られた、幾何学的で造形的な妙のある遊具。月のクレーターのような水場。ピラミッドのような山。「北海道らしさ」を出すための木々も、幾何学的に仕切られた土地に植えられているため、「文化的本質」なるものを感じさせる景色を生み出すことなく、自然主義的な模倣とは異なるような全体の造園意図と見事に調和している。何も再現せず、特定の歴史も感じさせず、そこに想像力を投影させれば無限の未来を思い描ける、そんな世界。幾何学的ではあるが無機質ではないそのユートピアに身体を浸す面白さと心地よさは、ディズニーランドほどの没入感を与えてくれるわけではないが、場合によっては、それとはまた別種の引力によって、私たちを子供時代へと立ち戻させる。
松木裕美が近著『イサム・ノグチの空間芸術』(淡交社、2021年)で浮き彫りにしているように、ノグチは明確な政治的理念を持って公共空間における彫刻の可能性を切り拓いた芸術家だった。初期活動では左派思想に共鳴し、労働組合関連のプロジェクトのコンペにも応募している。抽象的なモエレ沼公園のうちに左派思想を読み解くことは困難だが、それでもそのコンセプトの誕生の歴史は、危機の時代に直面し続けてきた彼の思想抜きに考えることはできない。庭や公園のような場所で、誰もが憩い、触れ、遊べる彫刻。その理念の根底には、老いも若きも、富める者も貧しき者も平等に美的空間を享受し共有し、彼らの視覚だけでなく触覚や聴覚を満たすような、ある種のユートピアへの志向が存在するのである。ノグチの児童遊園は、人々が新たな共同体を立ち上げ、新たな遊戯=実演を生み出すような、いわば芸術の受け手が作り手ともなり得る創造の場としても、構想されたのである*2。
私が今回の記事と、続く2回の記事の、計3回にわたって論じたいことは、二つある。第一に、ノグチの設計によるモエレ沼公園のタイプのユートピア思想が、20世紀前半の芸術家たちにおける「おもちゃ」の表象のうちに潜在的に存在していたということであり、そして第二に、そうした思想が、現実の理想主義的再現としてのユートピアに対し批判的な考察を迫るものであったという点である。もちろん、彼らが「おもちゃ」のうちに見出したユートピアもまた、ディズニーランドと同様、レジャーランドとしては機能するが、永遠に住めるわけではない。死と苦痛からの解放が約束されているのは、閉園までの時間、遊びが終わるまでの時間なのである。ユートピアとは、結局のところ、この語を生み出したトマス・モアの1516年の小説『ユートピア』において示唆されているように、「良い(eu)場所(topos)」であると同時に「どこにもない(ou)場所(topos)」なのだ。だからこそ私たちはそこで遊ぶ束の間の時間を、可能な限り全力で愛おしむ。問題になるのは次の点だ。すなわち、モダニズムの芸術家たちが生み出したユートピアが提供するのは、一体どのような遊びなのか。ここでは、未来派とキュビスムという二つの芸術における取り組みから考えてみよう。
未来派における感覚のユートピア
2000年にパリのフランス国立図書館で開催され、翌年ニューヨークの公立図書館に巡回した記念碑的な展覧会『ユートピア 西洋世界における理想社会の探求』において、20世紀のセクションの冒頭を飾ったのは未来派の作品の数々だった。1909年に、詩人マリネッティにより発せられた「未来派宣言」には、戦争や暴力の肯定、破壊の美学などの他に、機械文明の礼賛が、その指針として掲げられた。古いものの解体を、機械文明が可能にした速度でもって推し進め、原始的な生命と直観の力を動力源にしながら新しいものを作り出すこと、それは、機械論と生命論という、本来は相容れないはずのものを接近させる思想だった。展覧会ではそうした接近こそ、抽象芸術を日常生活の中に浸透させようとしたキュビスムの画家フェルナン・レジェや、エル・リシツキーをはじめとするロシア構成主義の芸術家たちのユートピア思想のヴィジョンにおいて共有され展開されたものであることが示されていた*3。
実際、マリネッティの未来派の指針を共有しそれぞれの分野に発展させた二人の画家ジャコモ・バッラとフォルトゥナート・デペロが、第一次世界大戦の最中である1915年に発表した「未来派による宇宙の再構築宣言」では、次のようなユートピア的ヴィジョンが示されている。そのヴィジョンとは、未来派の諸々の実践によって「宇宙を再構築すること、すなわち宇宙を活性化し、全体として再構築すること」であり、「触知できないもの、計量できないもの、そして知覚できないものに、骨格と肉体を与える」というものである。それは現在の宇宙に存在している事物を模造するのではなく、むしろそうしたものの「抽象的な等価物」を「われわれの霊感の赴くままに組み合わせ、造形複合体を作り上げて、それに動きを与える」ことで実現する*4。玩具の分野においても、汽車や人形やおままごとの食器など現実に存在するもの再現的なミニチュアではなく、笑いと柔軟性、想像力、感受性を引き出すような「造形複合体」の有効性が唱えられた*5。
こうした玩具を体現するものがあるとすれば、デペロが1917年に構想し、翌年ローマのピッコリ劇場で上演された「造形バレエ」に使用されたマリオネットを挙げることができるだろう。そこでは、鮮やかな色で彩られ、丸や四角といった基礎的な幾何学的形態を組み合わせた木製のマリオネットが音楽に合わせて動き、抽象的な舞台に新しい宇宙を作り始めるのである。マリオネットの原型は1918年の上演のちに失われてしまったが、彼の1918年の絵画《私の造形バレエ》(個人像)には、その楽しげな様子が描かれている。
ただ、未来派たちの描くユートピアのヴィジョンには、ともすれば容易にディストピアに転じるような危険性がつきものだ。バッラとデペロは同じ1915年の宣言の中で、「戸外で動かす巨大な、危険で攻撃的な玩具」によって、「闘争や戦争に向かう肉体的勇気を持つ」子供の育成を理念の一つとして掲げている。こうした玩具は、結局のところ、国家の将来を支える子供の育成という功利主義とも無関係ではないのだ。だからこそこの玩具は大人に対しても、「若く、活動的で、快活で、物にこだわらず、何事にも対応でき、疲れを知らず、本能的かつ直感的に保つ」効果を発揮するという*6。遊びによって鍛え上げられるのは、国家のために戦う強靭な肉体であり、革命に奉仕する精神である。そうした人々で構成される世界が実現した場合を想像してみよう。若くも快活でもなく、何事にも対応できず、いつも疲れていて本能も直感も枯れた者は、このユートピアに喜んで迎え入れてもらえるのだろうか。
30歳のマリネッティなら、未来派のユートピアにそうした人々の居場所は確保されていない、と、言うだろう。32歳のマリネッティは、1909年の「未来派宣言」ですでに、10年後の自分達を想像して、「われわれが40歳になったとき、われわれよりも若くて勇敢な人たちが、使えないマニュアルのようにわれわれを屑籠に捨ててくれればいい」と記している*7。「未来派宣言」でこの後に続くのは、未来の若者の熱狂により未来派の夢が解体されることを訴える、マリネッティの逆説的な願いだ。つまり、破壊を通じて未来派のユートピアが継承されるのであれば、マリネッティが生み出した未来派もまた、未来の芸術家たちによる破壊を免れ得ない、というのである。未来派は、成立の初期段階から、未来におけるおのれの解体を織り込んでいたのだ。未来派のユートピアは、結局のところ、安定した社会を望む実現可能な指針なのではなく、活力に満ちた若さだけが持つことのできる束の間の夢でしかないのである*8。
だが実際に40代に突入したマリネッティは、決してユートピアを立ち去ったわけではなかった。むしろ追い求めるべきユートピアの内実の方が、彼に合わせて変化したと言えるかもしれない。彼は1921年に発表した「触覚主義」で、感覚のユートピアとも呼ぶべきもののアイディアを示している。
「触覚主義」の文章には、第一次世界大戦の悲劇が暗い影を落としている。未曾有の被害をもたらした近代戦争の後、人々は二つのやり方でパラダイスを求め始めたとマリネッティは言う。一つは「物質的な健全さ」を追求する大多数の人々による理想郷の探求だ。マリネッティによれば、彼らは「コミュニストのパラダイスという革命的征服」に向かった。もう一つは芸術家や思想家といった「少数派」による理想郷の探求である。感じやすい心を持つ彼らは、戦争の傷跡を引きずり、「洗練された悲観主義」へと深く沈み込み、「コカインやアヘン、エーテルといったものの人工的なパラダイス」に向かう*9。
どちらの陣営も未来派の求めるものとは異なるのだと、マリネッティは言う。なぜならば多数派も少数派も、未来派が推進していた機械の力や進歩、速さに背を向け、揃いも揃って「野蛮な生活への回帰」を目指しているからだ*10。戦後の未来派が目論んでいるのは、「多数派が試みるようなあらゆる革命的攻撃」をより洗練されたやり方で追求し、少数派の人々が人工的なパラダイスによって押し殺そうとしている生命を取り戻すことなのである。「戦時の病」を癒し、「人類に新しく滋養のある喜びを与えること」こそ、未来派の目的なのであり、そのためには「コミュニケーションと人間同士の融合を強化」し、「愛と友情のうちにある彼らを離れ離れにする距離と障害を破壊する」ことが必要になる*11。マリネッティはこうした主張が、戦前の未来派の試みの延長線上にあることを明らかにしているが、戦後まもなく発表されたこの「触覚主義」からは、明らかに戦前のマリネッティの諸宣言にあった暴力的で好戦的なトーンは消えている。
さて、「愛と友情」により結ばれた人々が「融合」するユートピアはどのように実現されるのか。彼はこれまでのように目と耳だけでコミュケーションを行うだけではなく、肌によっても互いの内面を伝え合わなければならないと述べる。そのためには、「握手や口付け、そして性交を、絶え間ない思考の伝達へと変容させる必要」がある。マリネッティは好戦的ではなくなったものの、こうした主張には別方向に振り切れるような彼らしい過剰さが健在だ。矛盾と摩擦を最大限にして人々の間の闘争を掻き立てるようなところが戦前の未来派宣言にあったとすれば、戦後のマリネッティの「感覚主義」には、分断をなくして他我の境界が融解する地点を目指すような、ある種の平和主義の局地を見出すことができる。
ただ、人々は耳と目による伝達には慣れているものの、触覚による伝達に関しては未開発なままである。だから「触覚術」を身につけるような「教育的尺度」を設定し、それぞれのレベルの触覚を開拓する必要があると、マリネッティは述べている。とりわけ重要視されたのが「掌」の感覚だった。掌の触覚を開拓する手段として彼が提案するのが、「触覚板」の利用である。さまざまな触覚を喚起する素材が貼り付けられたその板を実際に制作したのは、マリネッティのパートナーであり未来派の芸術家でもあったベネデッタ・カッパだ*12。現存する「触覚板」である《パリ-スーダン》(グッゲンハイム美術館)には、スポンジやワイヤー、綿、ブラシといった荒い手触りを持つものが「スーダン」に見立てた側に配置され、絹やビロード、羽といった滑らかな手触りを持つものが「パリ」に見立てた側に配置された。そして両者を隔てる中央の「海」の部分には、銀紙が貼られた。この板に手を置き、多様な「触覚価値」を知覚することで、人々は「掌の旅行」ができるようになるのである*13。
美術史家フランチェスカ・バッチは、触覚を含む五感を刺激するような教育を重んじた同時代のイタリアの教育学者マリア・モンテッソーリの影響が、マリネッティとカッパによるこうした触覚の開発方法にも表れていると指摘している。モンテッソーリ式と呼ばれ世界で広く親しまれた彼女の1909年の著書『「子供の家」の幼児教育に適用された科学的教育学の方法』を、教育学を学んだベネディッタ・カッパが読んでいた可能性は高い。カッパは第一次世界大戦中にはローマで子供の教育にも携わっている。モンティッソーリはその教育方法の中で、片側に滑らかな面、もう一方にサンドペーパーを貼った面を持つ長方形の板を触らせることを提案しており、まさにマリネッティとカッパの「触覚板」を予見していることに、バッチは注意を促している*14。戦争の傷を癒すために、子供の感受性豊かな掌を取り戻して、肌で感じることを学び直し、人々との連帯を取り戻すこと。それこそ、マリネッティとカッパが「触覚板」を通して試みていたことだったのだろう。
抽象的な形の素材で刺激された感性を媒介にして人々との新たな結びつきを手探りで探ろうとするその理念は、まさに、冒頭で述べたノグチのプレイ・グラウンドの先駆けであるようにも思われるし、連載第4回の記事「機械的な手と建設者の手」で紹介したモホイ=ナジの「触覚訓練」は、マリネッティの試みを受け継いでいるように見えるだろう。ただマリネッティをノグチやモホイ=ナジと隔てる境界線は、つねに意識する必要がある。なぜなら他者との融合を望むマリネッティの思想には、ファシズムの全体主義と共鳴する危険性が潜んでいるからだ。マリネッティはイタリア・ファシスト党の初期加盟者のうちの一人であり、1919年には『ファシスト宣言』の共同執筆者となっている。マリネッティの感覚のユートピアは、ファシスト的な理想社会と地続きだった。これに対しノグチやモホイ=ナジにおける五感の開拓は、必ずしも他者との融合を目的としていない。むしろ容易には融合し得ないものとの絶え間ない対話というプロセスそのものが、そこでは重要であるように思われる。
ピカソのユートピアと「貧しき者の玩具」
容易には融合し得ないものとの対話。融合を目的としない、終わりなき対話を展開する場の構築。そうした試みはピカソの第一次世界大戦後のいくつかの作品にはっきりと認められる。そこにはもちろん、前回の記事で論じたような、奏でられない楽器を奏で、食べられない葡萄を味わおうとする私たちの衝動を引き出すキュビスムのゲームが前提とされている。この点で注目されるのは、1919年から20年の間に制作されたピカソの素描の中に認められる、キュビスム風のギターと古典的な手のイメージの並置である*15。例えばパリのピカソ美術館にある一枚《静物と手の習作》を見てほしい。グアッシュで淡い着色を施されたキュビスムの立体作品に、鉛筆で陰影のつけられた手が差し伸ばされている。手はこれからコップを握り、ボトルの酒をそこに注いで口元へと運ぼうとしているのかもしれないし、ギターを手にして奏でようとしているのかもしれない。いずれにせよそこにあるのは、同じ空間には共存し合えない二つの事物の出会いが、絵画という虚構空間では可能になるかもしれないという、ピカソの期待の表れである。これらの作品群に認められるそうした可能性の探究こそ、「ピカソのプロジェクトの核」であり、そこに切り拓かれる新たな創造の場こそ、「彼のユートピア」なのだと、美術史家のT. J. クラークはその著書『ピカソと真実』において述べている。
ピカソが彼自身の感覚のユートピアで繰り広げるゲームには、教育的な目的は存在しない。それはキュビスムのように知的な思索を掻き立てる場合もあるが、時には驚くほど無邪気なものとなる。無邪気さの極地にある作品の一つが、パリのピカソ美術館にある《蝶のコンポジション》(1932年)である。針金で作られた人、そこに重ねられた布の服。貼り付けられた本物の葉と蝶。白い羽の鱗粉という、まだ生々しい生命の痕跡を残した蝶は、白い絵の具とは明らかに異なる存在感を放っている。針金で作られた小さな人間は、その蝶と戯れ遊ぼうとしている。だが死んでしまった本物の蝶と、初めから生きてなどいない針金の人間が触れ合えるのは、唯一、ピカソの想像世界においてなのであり、彼のユートピア、つまり「どこにもない場所」においてなのだ。この無邪気なイメージを見た私たちは、気づけばそのユートピアに入り、それらのイメージを想像の中で動かして遊ぶことになるだろう。かつては生きていたものの残骸を玩具にする罪悪感を心の片隅に感じながら。
この作品を見るたびに思い浮かぶのは、ボードレールが「玩具のモラル」で触れている「貧しき者の玩具」である。1853年に初めて発表されたこのテキストの中で、ボードレールは玩具を使った遊びが、子供にとっては初めての芸術実践であるのだとした。なぜなら子供は、どんなに単純で安価なもの、例えば一本の糸や数本のピンでも、想像力を逞しくして自分の世界を構築する素材にすることができるからだ*16。そうした「貧しき者の玩具」こそ、単純さによって子供の想像力を掻き立てる。それは場合によっては、美しく飾られた富める者の玩具をも凌駕する魅力を放つ。そのことを示す逸話としてボードレールが引き合いに出すのが、貧しき子供の遊びを見つめる裕福な家庭の子供の眼差しである。自分の美しい玩具もそっちのけで、鉄の柵越しに見つめる小綺麗な身なりの子供の視線の先には、生きた鼠で遊ぶ「洟たれ小僧」の姿があった*17。単純な玩具の中でももっとも単純なもの、貧しき者の玩具の中でも最も飾らないもの、それは生そのものの中から選び取られた玩具だった。
1937年にパリ万博のスペイン館のために描かれた《ゲルニカ》は、一見すればそうした無邪気さの対極にあるように思われる。だが実はそれは、それ以前にピカソが開拓していた感覚のユートピアの延長線上にある。このことを最後に見ていこう。
ナチスによるスペインのバスク地方の爆撃のニュースを知ったピカソは、一般市民を犠牲にしたこの悲劇を題材にして《ゲルニカ》を描いた。ただしピカソの作品は、タイトルこそゲルニカの爆撃に言及するものであるにせよ、実際の出来事をルポルタージュ的に伝えるイメージとは程遠いものだった。逃げ惑う女と馬、死んだ赤子を抱え絶望の最中にある女、立ちすくむ牛、横たわる兵士。そうしたモチーフが、禁欲的な白と黒のモノクロームで彩られた。その難解な様式と謎めいたモチーフの取り合わせから、この作品については多くの研究がある。ある者はそこに中世の写本に描かれた「黙示録」の場面からの影響を認め、ある者はアングルやダヴィッド、ドラクロワらによる物語画からのモチーフの借用を指摘した。牛や馬が象徴するものについても諸説ある。
この作品の特徴は、そうした象徴性の複雑さにのみあるわけではない。親密さを感じることを鑑賞者に許さない厳しさは、この作品の重要な要素であり、そのことは作品の意味内容よりもその形式において表れている。T. J. クラークはとりわけ、その著書『ピカソと真実』においては、ドラ・マールによって撮影されたピカソの制作の段階に認められる空間表現の変化に注目して分析しながら、画家がいかに迷いと試行錯誤の中で巨大な画面を描き進めていたのかを論じている。ピカソは最初、屋外を舞台にしようとしていたが、舞台は最終的に、電灯によって照らし出される室内空間のような場所に移された。正確には内か外かもわからない、あやふやな空間である。場面が屋外であることを示すかのように、画面右側には燃え上がる建物、その隣には女性が顔をだす窓の上に瓦が見える。だが画面の四隅には室内の壁の存在を感じさせる斜めの線が入れられ、画面右端には扉が描かれている。この空間の奥行きは存在するが、極めて狭いものだ。そこは近づいて鑑賞することを求める浅浮き彫りの空間である。だが近づきすぎると今度は抽象的なカンヴァスの平面が現れる。そうした効果を確かめ実験するかのように、ピカソは、制作の途中でカンヴァスにモチーフの形に切り抜いた壁紙を部分的にあてがっていたことを、クラークは指摘している*18。
そこではまさに、虚構空間で諸感覚を戯れさせるピカソの作品のうちにクラークが認めたような実験的な「彼のユートピア」の場が、息づいていたのである。手を伸ばせば入れそうな空間だが、心の手を伸ばした途端に絵の具が塗られた平面が立ち現れる。簡単にはそこに没入することは許されない。私たちは逃げ惑う人々に共感することはできるが、その共感はつねに遅れを伴い、しかも長くは続かない。だがそうしたすべてに抗して、想像し難いものを想像し、諸感覚を動員するよう、この作品は私たちに呼びかけてもいる。
ピカソが手探りで辿り着いた、浅い奥行きの圧縮された空間は、キュビスム的な空間であると同時に、第12回の記事「セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(後編)」で取り上げたセザンヌの「吐き気すらもよおす」空間を受け継いでいる。セザンヌの描くサント・ヴィクトワール山を眺める、アメリカのミニマリズムの彫刻家ロバート・モリスは、幼年期への回帰も自然との同一化も求めようとはせずに、心の指で記憶の場を名づけ直し、自らの触覚によってセザンヌの絵の中の風景を新しいコードに置き換えた。同様にしてピカソの描く《ゲルニカ》も、過去の悲劇の正確なヴィジョンは与えないが、その浅い奥行きの中で人や獣の身体の厚みを見る者に類推させ、爆撃の下で逃げ惑い恐れ慄き悲嘆にくれる人の痛みを、鑑賞者自らの身体感覚とともに想像するよう求めている。そうして得られたヴィジョンは、過去の悲劇の類似物でしかない。だがこの類推の作用によってこそ、私たちは、私たち自身の固有の限界を抱えた身体という、見通しを欠いたローカルな地点から、記憶と知覚を頼りにして過去を手探りで知ろうとすることができる。《ゲルニカ》はその可能性を探る実験的舞台なのだ。
つまり《ゲルニカ》とは、過去の真実を伝えることを目的とした歴史画でも、観客に政治行動を直接的に誘発することを目的としたプロパガンダでもない(もし《ゲルニカ》が伝統的な歴史画やプロパガンダであることをピカソが望んだのであれば、現存する作品とは別の形式をとったことだろう)。それは、過去の悲劇を目の当たりにした人々の今は亡き存在を、そうした悲劇の遠くにいる私たちの身体へと近づけるための、人工的な舞台装置なのである。近接性を要求しつつ親密さを拒むこの画面は、極限まで色彩と装飾と再現性を排除することで、ある種の「貧しさ」を導入した。そのことによってこそこの画面は、単純な感情移入や直裁的な没入感を抱くことを阻み、スペクタクルとして消費されることを拒みながらも、実際の命を持った肉体が経験した破壊の恐怖を想像するよう私たちに誘いかけている。この浅い奥行きの空間に心の手を伸ばして、決して一体化することなどできない人々の身体の痛みを、私たち自身の体で想像してみるよう、誘いかけているのである。
それが私たちに実際に可能かどうかではなく、私たちにそうした可能性が残されているということが、ここでは重要なのだ。クラークは『ピカソと真実』を次のような言葉で結んでいる。
私が主張できるのは、彼がこの難題に立ち向かったということ、つまり《ゲルニカ》においてついに、人間や動物を私たちの近くまで来させて、地〔訳注:原著で用いられている語「ground」には、「図」に対する「地」と、「地面」の二つの意味が含まれている〕の上に位置付ける方法を見つけたということだ。そして地とは、正確には外でも内でもなく、まさに世界が破壊されるその瞬間を迎えた底辺〔訳註:原著で用いられている語「floor」には、《ゲルニカ》に描かれたタイル張りの「床」も指し示している〕なのである。さらにそこでは、女たちや獣たちは、すべてに抗して、直立して何が起こっているのか見ようとする闘いの最中にあった。私がこのことすべて(この重大さ)を主張し、あなたを説得しようと望むことができるということだけで、十分すぎることなのだ*19。
ピカソが私たちに残してくれたこの可能性は、たとえ作品そのものにある種の「貧しさ」が宿っていたとしても、かけがえのないものである。ピカソは、かつて子供であった大人たちに、「貧しき者の玩具」を提供し続けた芸術家だ。この玩具は前衛文化におけるユートピアには欠かせないものであり、未来派やモホイ=ナジやイサム・ノグチの追い求める感覚のユートピアとも、決して無縁ではない。だがピカソの《ゲルニカ》は子供時代への素朴な回帰を促しはしない。そこにはむしろ、子供時代を終えた者でしか感じることができないような、失われてしまいもはや取り戻せもしないものを振り返る「喪」の振る舞いがある。とはいえそこには感傷的なノスタルジーもない。教育的な目的もない。過去の出来事への素朴な感情移入の手がかりも、未来に生かすべき教訓も、そこには示されていない。あるのは、彼が仕組んだ舞台上のゲームに参与するよう呼びかける独特の引力、声なき声だ。このゲームは決して心踊る遊びではない。爆撃の恐怖と愛する者を失う悲しみを想像するプロセスを伴うものだからだ。それは「どこにもない(ou)場所(topos)」ではあっても、「良い(eu)場所(topos)」ではない。
それでもなお、楽しむためではなく痛みと苦しみを想像するためにこそ、私はそこに手を差し伸ばしてしまう。すると馬も牛も、象徴物ではなくなり、彼らの驚愕する眼差しは私の目となる。我が子を失う母親の絶望は、紋切り型のアイコンではなくなり、私の悲しみとなる。逃げ惑う人の叫びは、私の叫びとなる。こうして人々に心の手で触れられるたびごとに、《ゲルニカ》という「どこにもない場所」は場を持つことになり、そこに描かれた人や獣は、厚みを持った身体を与えられる。もちろん私の身体がイメージとのあいだに築く共鳴と共振の関係性は、長くは続かない。《ゲルニカ》は結局、実際に手を伸ばしても絵画平面に阻まれるような、虚構の舞台なのだ。他我の境界は完全に崩れ去ることなく、自分が経験する共感は個人的な想像にすぎない、という意識へと、私は立ち退かなければならなくなる。現実の痛みは私の想像よりも耐え難く、現実の絶望は私の想像よりも深かったはずだ。そのことを確認してから、私は展示室をあとにする。それでも展示室を去ろうとする私の身体は、この虚構の舞台に身を浸す前とは別様に世界を感じることになる。
現代世界が今まさに抱えている痛みや苦しみに共感を寄せるのに《ゲルニカ》が必要不可欠であるというわけではない。《ゲルニカ》が悲劇的な出来事を想起するためのもっとも効果的な舞台装置だと言うつもりもない。ただこの大画面は今でも、想像し難い苦しみを、それでも想像する経験を与えてくれる可能性の一つであり続けている。今は亡き者の痛みを理解しようと手を伸ばす者に向けて開かれた、仮設舞台の一つであり続けているのだ。
注
*1 Louis Marin, « Dégénérescence utopique : Disneyland », Utopiques : jeux d’espaces, Paris, Les Éditions de Minuit, 1973, p. 297-324(ルイ・マラン「退廃のユートピア ディズニーランド」『ユートピア的なもの 空間の遊戯』梶野吉郎訳、法政大学出版局、1995年、332〜364頁)
*2 松木の著書の中でも、アメリカでの児童遊園のプロジェクトを扱った最終章を参照のこと。松木裕美「中心の再創造――アメリカ都市の危機に挑む」『イサム・ノグチの空間芸術 危機の時代のデザイン』淡交社、2021年、181-241頁。そこでは、ノグチの作品が冷戦下のアメリカでいかに読み替えられていくのかについても論じられている。なお松木は、ノグチの没後に完成されたモエレ沼公園については触れていない。企画段階で作家が逝去したからである。その建設の経緯については次に詳しい。川村純一・斉藤浩二著『建設ドキュメント1988――イサム・ノグチとモエレ沼公園』学芸出版社、2013年。
*3 Roland Schaer, “Utopia and Twentieth-century Avant-gardes,” Utopia: The Search for the Ideal Society in the Western World, exh. cat., The New York Library, 2000, p. 278-289.
*4 英訳を参考にしやや表現を変えた。Giacomo Balla, Fortunato Depero, “Futurist Reconstruction of the Univers 1915,” in Umbro Apollonio(dir.), Futurist Manifestos, Boston, MFA Publications, 2001, p. 197.ジャコモ・バッラ、フォルチュナート・デペロ「未来派による宇宙の再構築宣言」(1915年3月11日)、浦上雅司訳、『デペロの未来派芸術展』東京都庭園美術館;大阪サントリーミュージアム、2000年、178頁。
*5 Apollonio(dir.), Futurist Manifestos, p. 199-200(邦訳、179頁).
*6 Apollonio(dir.), Futurist Manifestos, p. 199(邦訳、179頁).
*7 F. T. Marinetti, « Manifeste du Futurisme », Figaro, 20 février 1909, p. 1.
*8 シュルレアリスムやシチュアショニスムにもそうした態度が共通することを指摘するサム・クーパーは、こうした前衛運動がユートピアを志向しながらも、同時にユートピアの実現不可能生を宣言し、そのことによってユートピアと敵対しさえする傾向を持つと述べている。Sam Cooper, “Enemies of Utopiaa for the sake of its realization,” in David Ayers, Benedikt Hjartarson, Tomi Huttunen and Harri Veivo (eds.), Utopia: The Avant-Garde, Modernism and (Im)possible Life, Berlin; Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2015, p. 17.
*9 次の英訳を参照。F. T. Marinetti, “Il Tattilismo” (Milan, 1921), in Lisa Panzera and Cinzia Blum(eds.), La Futurista : Benedetta Cappa Marinetti, Philadelphia, Goldie Paley Gallery and Moore College of Art and Design, 1998, p. 54.
*10 Ibid.
*11 Ibid., 55
*12 F. T. Marinetti, La grande Milano, Tradizionale e futurista. Una Sensibilità italiana nata in Egitto, Milan, Mondadori, 1969, p. 263-267.
*13 F. T. Marinetti, “Il Tattilismo” (Milan, 1921), in Panzera and Blum(eds.), La Futurista, p. 55-56.
*14 Francesca Bacci, “In Your Face: The Futurists’ Assault on the Public’s Senses,” in Patrizia Di Bello and Gabriel Koureas (eds.), Art, History and the Senses, 1830 to the Present, London, Routledge, p. 92-93.
*15 T. J. Clark, Picasso and Truth: From Cubism to Guernica, Princeton University Press, 2013, pp. 44-45. この著書は、2009年春にメロン・レクチャーとして行われた連続講演の原稿がもとになっている。
*16 Charles Baudelaire, « Morale du joujou » (Le Monde littéraire, 17 avril 1853), dans Claude Pichois (éd.), Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1975, p. 582-584. 次の邦訳を参考にした。ボードレール「玩具のモラル」『ボードレール全集IV』阿部良雄訳、筑摩書房、1987年、116頁。
*17 Baudelaire, « Morale du joujou », dans Pichois (éd.), Œuvres complètes, p. 584-585(邦訳、117〜118頁).
*18 T. J. Clark, Picasso and Truth, from Cubism to Guernica, Washington, National Gallery of Art; Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2013, p. 274.
*19 Ibid., p. 282.
》》》バックナンバー ⇒《一覧》
第1回 緒言
第2回 自己言及的な手
第3回 自由な手
第4回 機械的な手と建設者の手
第5回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(前編)
第6回 時代の眼と美術史家の手――美術史家における触覚の系譜(後編)
第7回 リーグルの美術論における対象との距離と触覚的平面
第8回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(前編)
第9回 美術史におけるさまざまな触覚論と、ドゥルーズによるその創造的受容(後編)
第10回 クールベの絵に触れる――グリーンバーグとフリードの手を媒介して
第11回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(前編)
第12回 セザンヌの絵に触れる――ロバート・モリスを介して(後編)
第13回 握れなかった手
第14回 嘘から懐疑へ――絵画術と化粧術のあわい
第15回 キュビスムの楽器の奏でかた、キュビスムの葡萄の味わいかた